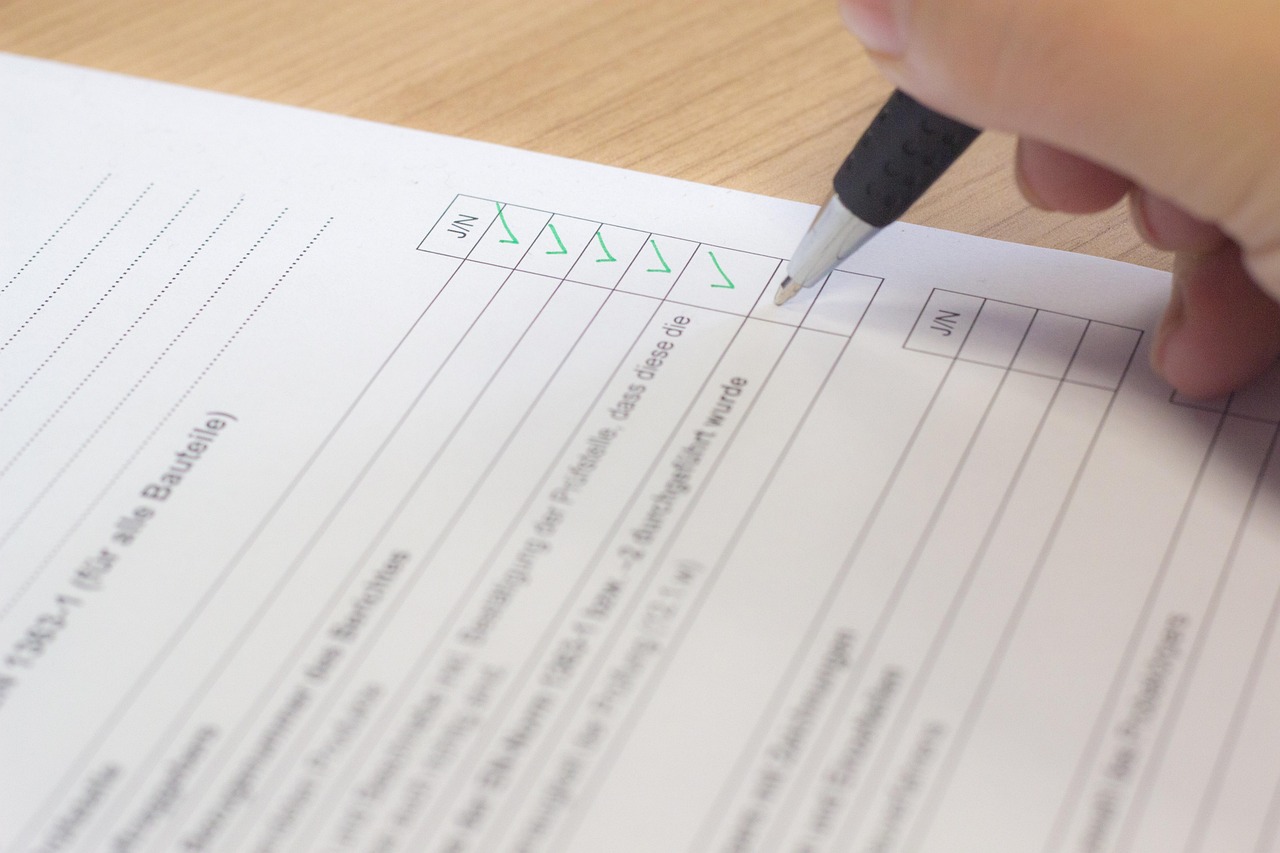注意点まとめ
【 技術士 二次試験対策 】
必須科目Ⅰ
必須科目は、課題、解決策、新たなリスク、倫理の4部構成です。それぞれの書き方をおさらいしましょう。
1.課題
課題のパラグラフは、以下の項目で構成します。
① 現状
例)「近年…である」、「我が国は、…している」などなど
② 問題点
例)「このため、…が懸念される」、「しかし、…が危惧される」
③ 必要性
例)「このような状況の中…が求められている」、「…するためには、…が必要である」
④ 結論
例)「よって、・・・の観点から、・・・が課題である」
それぞれを一行程度で書けば、あら不思議もう書きあがってしまいます。現状や問題点の説明が長くなる場合は、必要性はすっ飛ばしてもOKです。
2.解決策
解決策のパラグラフは、以下の項目で構成します。
① 目的→やること
例)「…するため、…する」
② 具体例
解決策は、シンプルな構成です。①は1・5行から2行程度、1文で書き上げてしまいましょう。肝心なのは具体例です。具体例=技術力とであることを肝に銘じ、具体的記述を徹底しましょう。
3.新たなリスク
このパラグラフで注意しなければならないのは、新たなリスクであること、すべての解決策に関連していること、この二つの条件が満たされているか、立ち止まり確認しましょう。リスクへの対応策は、解決策と同様、具体的な記述を心掛けましょう。
4.倫理
倫理も、実にシンプルです。技術士倫理綱領に沿って解答すると良いでしょう。ここは、超簡単なのでボーナスステージです。時間がなく、もうヤバいとなった場合は、以下のフレーズを書いておきましょう。
「業務にあたっては、常に社会全体における公益を確保する観点と、安全・安心な社会資本ストックを構築して維持し続ける観点を持つ必要がある。業務の各段階で常にこれらを意識するよう留意する。」
選択科目Ⅱー1
ここは、書くことがあまりありません。1枚しかありませんし、構成も何もありません。聞かれたことを漏れなく書く。これだけです。多くは、2つの事柄を問われることが多いので、それぞれを見出しに設定し、知っている知識を絞り出しましょう。
選択科目Ⅱー2
選択科目Ⅱー2は、調査・検討事項、手順、調整方策の3部構成です。この問題で苦戦するのは、スペースがない!ということです。特に、検討ステップが多い業務ですと、手順のスペースをたくさん用意する必要があります。
手順は端折るわけにはいかないので、漏れなく書きます。そのためには、端的に説明することが重要です。短く的確にという記述は、結構な難易度です。余計なことは、一切書いてはいけません。聞かれていることのみに答えましょう。
1.調査・検討事項
注1 「検討」は整理事項に変わる場合もあるので問題をよく読みましょう。
注2 調査ごとに見出しをつけましょう。
注3 調査事項を列記して、それを踏まえて何を検討(整理)するのかを書きましょう。
2.手順
注1 手順は好き勝手に書いていいわけではありません。手引き、ガイドライン、法定手続き、指針などルールに沿った記述が必要です。
注2 手順には、必ずしも留意点や工夫点を書く必要はありません。スペースを勘案しながら、ここぞというモノに限定して書くのも一つの手段です。
注3 調査・検討項目で記述してあっても、手順を示す必要があるので、省略せずに書きましょう。
3.調整方策
注1 誰とどんな内容を調整するのかだけでなく、効率的・効果的な調整方策を聞かれるので、効率的・効果的な方法であることを説明しましょう。
注2 スペースにもよりますが、調整相手ごとに整理して書くと分かりやすく説明できます。
注3 具体的な説明を心掛けましょう。
例)× 住民説明会を実施する
〇 住民に対しては3D都市モデルを活用して視覚的に説明を行う
選択科目Ⅲ
注1 構成は、必須科目Ⅰと同様です。必須科目との違いは、倫理がないことです。このため、解決策やリスクの記述に厚みを持たせると良いでしょう。
注2 選択科目で最も重要なのは、専門科目の記述をすべてのパラグラフに盛り込むことです。これがメチャクチャ重要です。専門的記述に全振りです。
注3 専門的知識は、マニアックな高度な知識ではありません。求められる記述(技術力)は、国の政策です(必須科目Ⅰも同じ)。
最後にスーパーテクニック
絶対にあきらめない!