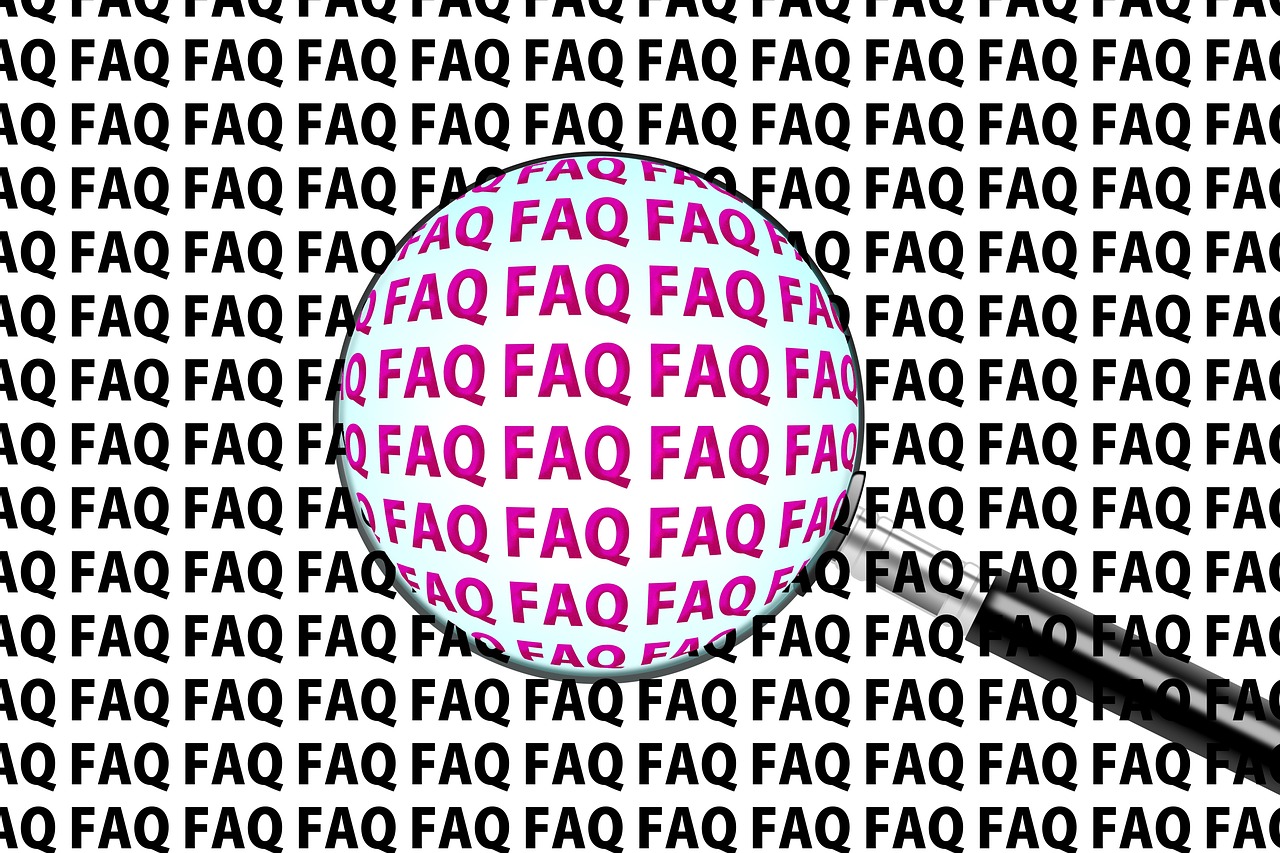口頭試験の質問主旨を把握せよ
【 技術士 二次試験対策 】
口頭試験FAQの添削
技術士二次試験の筆記結果は全員お手元に結果通知が来たと思います。今年は添削指導を行った受験生の約半数が合格という、全国平均10%前後の合格率を踏まえれば、なかなかの成果となりました。とはいえ、指導した全員を合格に導きたかったという思いは尽きません。
試験は筆記力だけでなく、構成力・論理性・現場感覚など多面的な力が問われるため、今後もより実践的な添削を心がけていきます。また、添削投稿者だけでなく、ブログを読んでくださる方々にも、読んだだけで対策のヒントが得られるよう、記事の構成や事例の提示にも工夫を重ねていく所存です。
私はこれまで、技術士試験を目指す多くの受験生に対して、筆記・口頭の両面から添削指導を行ってきました。その中で感じるのは、「実務経験が豊富であっても、それを試験の文脈で適切に表現することは、まったく別のスキルである」という現実です。実際、現場での優れた成果や判断が、試験の解答としては伝わりきらず、評価に結びつかないケースも少なくありません。
本日は、特に多く見られた“つまずき”や“誤解”を整理し、合格に向けて押さえておくべき注意点を紹介します。筆記試験の構成力、口頭試験での応答の仕方、そして技術士に求められるコンピテンシーとの接続──これらをどう捉え、どう表現すべきかを解説していきます。それでも、不安な人は、FAQの添削をご依頼くださいね(添削サービスはコチラ)。
技術士試験は、単なる資格取得のための試験ではなく、技術者としての姿勢や倫理観、社会との関わり方を問う「プロフェッショナルの証明」です。だからこそ、表現の一つひとつに意味があり、そこに“技術士らしさ”がにじみ出ているかどうかが、合否を分けるのです。
技術士試験における「問いへの的確な応答力」の重要性
問いの構造を見極める力
技術士試験では、筆記・口頭ともに「問いに対して的確に答える力」が強く求められます。添削結果から見えてきたのは、受験者が「問いの構造」を誤認してしまうケースです。たとえば「コミュニケーションをどのように取っていますか。事例を挙げてください」という問いに対して、事例の前に抽象的な手法論を述べてしまうと、構造的にズレが生じます。まずは事例を提示し、その中で手法を説明するのが筋です。
コンピテンシーとの接続を意識する
技術士試験では、単なる経験談ではなく「技術士としての資質・能力(コンピテンシー)」に照らした説明が求められます。たとえば「リーダーシップ」では、「多様な関係者の利害を調整し、合意形成を図ること」が定義されています。にもかかわらず、「提案した」「説明した」だけでは不十分で、「どうやって納得させたか」「どのように主導したか」まで踏み込む必要があります。
口頭試験では「端的さ」と「再現性」が鍵
口頭試験では、限られた時間の中で明快に伝える力が問われます。添削結果からは、「抽象的な語り口」や「定義の持ち込み」によって、問いに対する応答がぼやけてしまう傾向が見られました。たとえば「リーダーシップとは〜」と定義を語るよりも、「誰に」「どう働きかけ」「どう合意形成したか」を端的に語る方が、評価者に伝わります。
技術士試験における「具体性と定量性」の説得力
「抽象語」ではなく「行動」と「成果」で語る
添削結果から浮かび上がった最大の課題は、「抽象語の多用」です。「工夫した」「配慮した」「スムーズに進めた」などの表現は、評価者にとっては空疎です。代わりに、「何を」「どうした」「どんな成果が出たか」を具体的に語る必要があります。たとえば「件数を〇件から△件に削増加させた」「約●万円のコスト縮減した」といった定量的な成果は、説得力を持ちます。
トレードオフの「葛藤」を描く
「トレードオフ」の問いでは、「何を犠牲にし、何を優先したか」という葛藤の描写が不可欠です。添削では、「両立できた」という結果だけが語られ、調整の苦労や判断の背景が抜け落ちているケースが目立ちます。技術士は「公益を損なわない技術判断」が求められるため、「安全性を優先し、コストを抑えるために既存設備を改良した」など、判断の根拠と倫理的配慮を明示する必要があります。
評価やマネジメントは「資源配分」と「要求事項の達成」で語る
評価やマネジメントに関する問いでは、「進捗管理」「リスク対応」などの要素が語られがちですが、それだけでは不十分です。技術士コンピテンシーでは、「資源(人員・設備・情報)の配分によって、品質・納期・安全性などの要求事項を満たすこと」がマネジメントの本質とされています。つまり、「どの資源をどう配分し、どの要求事項をどう満たしたか」を語ることが重要です。
技術士試験における「倫理・継続研さん・失敗の活かし方」
技術者倫理は「公衆の安全・健康・福利」から語る
技術者倫理に関する問いでは、「誠実性」や「持続可能性」などの抽象的な価値を語る傾向がありますが、技術士倫理綱領では「公衆の安全・健康・福利の最優先」が明記されています。したがって、「安全性を確保するために、住民と利用者間の利害調整を行い、継続モニタリングを実施することで理解を得た」など、具体的な行動と倫理的判断を結びつけて語る必要があります。
継続研さんは「自分の学び」を中心に
「継続研さん」の問いでは、「人材育成」や「組織貢献」に軸足が置かれすぎる傾向があります。しかし、問いは「自分が何を学び、どう成長したか」を聞いています。たとえば、「週1回の研修で設計ミス事例を学び、自分の設計に反映させた」「特許出願を通じて技術の社会還元を実感した」など、自分の学びと行動を中心に語ることが重要です。
失敗は「波及効果」まで語る
失敗経験の問いでは、「何を失敗したか」が曖昧なケースが多く見られました。失敗とは「結果」であり、「原因」ではありません。たとえば「設計整合が取れず、手戻りが発生した」という結果を明示し、その原因(準備不足)と対策(手段の仕組み化)を語ることで、説得力が増します。さらに、「他業務への展開」「波及効果」まで語ると、技術士としての再現性が伝わります。