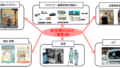添削LIVE
【 技術士 二次試験対策 】
働き方改革をテーマとした出題の可能性
本日の添削LIVEは、以前投稿のあった「働き方改革」をテーマとした予想問題の論文を完成まで一挙に見ていきたいと思います(問題や以前の論文はコチラ)。最後は、合格水準を満たす論文になっていますので、みなさんの参考になると思います。
さて、そんな中、働き方改革というテーマについて考えてみましょう。実は、令和6年度の試験で最も注目していたテーマがこの働き方改革です。私自身も、一押しテーマということでご紹介してきました。これは、働き方改革関連法によって時間外労働の上限規制が2024年4月1日に建設業にも適用される(いわゆる2024年問題)といった背景があったからです。
これは、時事的にはバッチリ過ぎると考え一押ししてきたわけですが、結果は国土形成計画と復旧DXにその座を奪われてしまいました。では、令和7年度の問題テーマとしての働き方改革は、その旬が過ぎてしまったのでしょうか?
否!私はまだまだ、その熱は失われていないと考えます。2024年問題の影響は、令和7年度で顕在化するわけで、それへの対応を問うてくることは十分考えられるからです。運輸部門で言えば、運転手不足が発生し、我ら建設業にあっては人手不足がもろに発生しています。
働き方改革は、労働者の多様な価値観に対応するでなく、この人手不足に対応するための効果も秘めています。なぜかと言いますと、余暇の時間を増やす、自由な就業時間、様々な人材活用といったダイバーシティの実現には、生産性の向上が必要となるからです。
この生産性の向上に関する必要性については、中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会基本問題小委員会の中間とりまとめ~担い手確保の取組を加速し、持続可能な建設業を目指して~において、次のような内容が示されています。
働き方改革を推進していくと同時に、物的・人的両側面での生産性の向上を図っていくことは業界全体の発展にとって不可欠である。(中略)近年発達著しい情報通信技術を業界全体で活用していくための枠組みを構築し、例えば作業員名簿作成等の事務作業や勤怠管理の効率化を図ることで就労環境の改善を図るともに、施工体制管理のさらなる徹底を目指すことが必要である。
働き方改革とセットで生産性の向上が説明されていますよね。さらに、重要なのが「情報通信技術を業界全体で活用」です。つまり、ICT技術というヤツですよ。どんな課題でも、結局このICT技術に収れんしていくというのが最近の傾向です。ICT技術に関する知識(具体例)は、多ければ多いほど良いです。
働き方改革・生産性の向上・ICT技術の三兄弟は、もはや桃園の誓いを立てたようなものです。また、これら3兄弟は、試験で大活躍する劉備・関羽・張飛と言えます。ぜひ、この周辺知識を強化することをお勧めいたします。
論文
「働き方改革」 チェックバック②
(1) 働き方改革を進めていくにあたっての課題
1) 適切な賃金の支払い
建設技術者の平均年収は、令和4年時点で約466万円であり、全産業平均約494万円を下回っている。賃金の低さは人材の流出につながり、さらに担い手不足や長時間労働が深刻化する①。したがって処遇の観点から適切な賃金の支払いが課題である。
① 担い手不足が深刻化するのは理解できますが、長時間労働が深刻化するのはなぜでしょう。賃金の低さとの関係が分かりません。また、課題には「適切な」とあるので、技能・経験に応じて適切に処遇される環境整備の必要性を述べてはいかがでしょうか(この場合、観点が重複気味なるので制度面としてはどうでしょうか)。
2) ワークライフバランスの確保
2024年労働基準法の改正により有給取得の義務化された②。しかし③災害時の対応や工期末の繁忙期など連勤が続く場合がある④。健康面や働く意欲面からも休暇は必要な時間である⑤。したがって健康面の観点からライフワークバランスの確保が課題⑥である。
② →「有給取得が義務化された」
③ 細かい話ですが、「しかし」、「したがって」といった接続詞の後ろには読点を打ちましょう。
④ 連勤とは連続して勤務することですから、連勤が続くとの表現に違和感があります。また、災害時は非常事態なので、例示として適切か疑義があります。さらに、これを問題点とするなら、課題は工事時期の平準化が課題のような気がします。この課題なら、共働き、働き方に対する価値観の変化といった現状を踏まえ、生活と仕事の両立ができていないといった指摘が必要です。
⑤ 休暇の必要性は、言わずもがなではないでしょうか。もっと、建設業の現状と問題点をフィーチャーしないと技術者としての立場になっていないと思います。
⑥ これも⑤と同様、まだ一般論を脱していないと思います。技術的提案とするために、ワークライフバランスを観点に、前述のとおり発注時期の平準化あたりを課題にしてはどうでしょうか。
3) DX化の推進
建設就業者は平成9年をピークに減少している。一方、紙ベースのやりとりや対面打合せなど昔からの慣習が残っている。そのためデータの管理や共有、日程調整や意思決定に時間がかかっていることから生産性向上の取組は急務である⑦。したがって効率化の観点からDX化の推進が課題である。
⑦ 生産背の向上が急務になっているのは、時間がかかっているからというより、労働力が少ないうえに業務効率が低いことが理由ではありませんか。→「・・・決定に多大な時間を費やしている。これらのことから、生産性の向上に向けた取り組みが求められている。」
(2)最重要課題とその解決策
最重要課題にDX化の推進を挙げる。DX化は即効性があり、企業の競争力を高めることにもつながるからである。以下に解決策を挙げる。
1)BIM/CIMの導入
BIM/CIMを導入し計画から維持管理までの建設プロセス全体の生産性を向上させる。3次元モデル⑧のデータベース化により、測量・設計データや竣工図などの情報を一元管理し、受発注者の情報共有を容易にする。3次元の視覚化⑨で既設構造物の接続部、支障物の位置確認、完成イメージを関係者と共有する⑩。また維持管理においては、各部材の損傷度などの点検結果を3次元モデルの属性情報に付与する。損傷度や損傷種類を色分け表示し、劣化原因や対策工法を速やかに検討する⑪。
⑧ これは3次元モデルではなく、点群データですかね。
⑨ こっちは「3次元モデルによる可視化」ですね。
⑩ 情報共有は前段で述べているので、重複気味ですね。情報共有だけでなく、他の効果も説明した方が良いでしょう。→「・・・の位置、完成イメージといった情報を活用し、業務を効率化と品質向上を図る」
⑪ 色分け表示することと、速やかに検討することがどのようにつながるのでしょうか。手段と結果がミスマッチに感じます(色分けは、緊急性や業務の優先順位等を分かりやすく判別するためといった目的が考えられます)。
2)ICT施工の促進
ICT施工により現場の作業効率化を図る。例えば、「施工のオートメーション化」により1人あたりの重機作業量を向上させる。1人のオペレーターが複数の建設機械を操作管理する。またAIを活用した画像分析でナンバーを読み取り、ダンプトラックの入退場の自動管理を行う。タイヤの泥落とし状況を判断し、不十分な場合はアラームで知らせる。さらに、建設現場に立ち入らず遠隔で建設機械の動作管理をすることで、場所にとらわれない多様な働き方ができる⑫。
⑫ 「遠隔で」と述べているので、「立ち入らず」は不要ですね(重複表現)。また、文末は可能性ではなく、やることとして書きましょう。→「建設機械の動作管理を遠隔化することで、場所に捉われない多様な働き方を実現させる」
3)行政手続きのデジタル化
行政手続きのデジタル化により、行政担当者・申請者の利便性を向上させる。例えば、特に申請件数が多い道路・河川占用申請をオンライン申請システムで完結させる。前回申請した履歴から繰り返し申請をすることで書き写す時間を削減する⑬。また占用料などの支払いにインターネットバンキングを活用し、支払い手段を増やす⑭。行政側はデータ管理により申請書の紛失リスクが減り、関係部署間での共有が容易となる⑮。
⑬ 効果を中心に説明していますが、解決策なのでまずはやることをきっちりと示しましょう。「例えば、申請件数が多い道路・河川の占用申請をオンライン化する。オンライン化にあたっては、申請から支払いまでの手続きを一括して行えるシステムを構築する。申請をオンライン化により、類似の申請手続きの簡略化や移動時間の削減することで、手続きに要する業務時間を大幅に短縮する。」
⑭ 手段を増やすとしているものの、支払い手段はネットバンキングだけであることが気になります。そもそも、支払い手段の多様化というより、ネット決済を可能にすることが主張すべき例ではないでしょうか。
⑮ 紛失リスクもありますが、より効果が見込まれるのは、データ管理が容易になる、窓口業務時間が削減されるといったことではないでしょうか。また、情報共有の目的がよく分かりません。
(3)新たなリスクと解決策
データ利用増加によるハッキングやサイバー攻撃のリスクが高まる。個人情報や企業機密情報の流出、重要インフラの停止の恐れがある。解決策として、複数対策の多層防御を講じる。入口対策はセキュリティソフトやファイアウォールを導入する。内部対策はログ監視や社内データの暗号化を実施する。出口対策は社外通信の経路の制限・ブロックを実施する。
(4)業務遂行において必要な倫理、社会の持続性
倫理の観点に関する要件は、常に公共の安全と福利を第一に考えることである。生産性向上を追い求めるあまり、安全性を損なうことやデータ不正・改ざんをすることは決して行わない。
社会の持続性の観点から省エネ・省資源化を図る⑯。例えば受発注者間のやり取りを情報共有システムで行うことでペーパーレス化を図り、紙消費量を減らす。ICT施工では、現場の丁張設置手間や高精度の土工仕上げにより手直しが減少するため、建設機械から排出されるCO2を削減できる⑰。このことからSDGsの目標13「気候変動」にも配慮することが要件である。以上
⑯ 倫理と同様に聞かれていることに対し明確に解答しましょう。→「社会の持続性の観点に関する要件は、省エネ・省資源化を図ることである」
⑰ これは、例示ではなく、ICT施工の効果を説明したものになっています。
「働き方改革」 完成
(1) 働き方改革を進めていくにあたっての課題
1) 適切な賃金の支払い
建設技術者の平均年収は、令和4年時点で約466万円であり、全産業平均約494万円を下回っている。賃金の低さは人材の流出につながり、さらに担い手不足が深刻化する。また、建設業は年功序列の傾向が強く、技能と賃金が連動していない。このため、適切な処遇改善に向けた環境整備が必要である。したがって、制度面の観点から、適切な賃金の支払いが課題である。
2) 発注時期の平準化
2024年労働基準法の改正により有給取得が義務化された。しかし、年度末に工事が集中するなど、依然として休暇取得が難しい時期がある。ダイバーシティをはじめ労働の価値観が変化している中、いつでも休暇取得できるよう、建設業では繁忙期の解消が求められている。したがって、ワークライフバランスの観点から、発注時期の平準化が課題である。
3) DX化の推進
建設就業者は、平成9年をピークに減少している。就業者数が減少しているにもかかわらず、紙ベースのやりとりや対面での打合せなど、旧態依然の慣習が残っている。そのため、情報の管理や共有、日程調整や意思決定に多大な時間を要している。これらのことから、生産性向上に向けた取組が急務である。したがって、効率化の観点から、DX化の推進が課題である。
(2)最重要課題とその解決策
最重要課題にDX化の推進を挙げる。DX化は即効性があり、企業の競争力を高めることにもつながるからである。以下に解決策を挙げる。
1)BIM/CIMの導入
計画から維持管理までの建設プロセス全体の生産性を向上させるため、BIM/CIMを導入する。BIM/CIM の3次元データを活用することで、測量、設計、出来形などの情報を一元管理し、受発注者間の情報共有を容易にする。また、3次元モデリングによる視覚化で、既設構造物の接続部や支障物の位置等の把握、並びに完成イメージの共有を行う。さらに、維持管理においては、各部材の損傷度などの点検結果を3次元モデルの属性情報に付与する。損傷度や損傷種類を色分け表示し、補修の緊急性や優先順位を明確にする。
2)ICT施工の促進
現場の作業効率化を図るため、ICT施工を促進する。例えば、建機のオートメーション化により、オペレーターが複数の建機を操作管理することで、一人当たりの作業量を向上させる。また、画像分析で搬出入車両のナンバーを読み取り、トラック等の入退場を自動で管理する。さらに、AIを活用することでタイヤの泥落とし状況を検知し、不十分な場合はアラームで知らせる。加えて、建設機械の動作管理を遠隔化することで、場所にとらわれない多様な働き方を実現する。
3)行政手続きのデジタル化
行政の負担軽減・申請者の利便性を向上させるため、行政手続きをデジタル化する。例えば、申請件数が多い道路・河川等の占用申請をオンライン化する。申請のオンライン化により、類似の申請を容易にするとともに、移動時間を削減することで、手続きに要する業務時間を短縮する。行政側は、オンライン化することで、窓口業務時間の削減、データ管理の効率化を図る。
(3)新たなリスクと解決策
デ ータ利用増加によるサイバー攻撃等のリスクが高まる。個人情報や企業機密情報の流出、重要インフラの停止が懸念される。解決策として、複数の対策を組み合わせる多層防御を講じる。入口対策は、セキュリティソフトやファイアウォールを導入する。内部対策は、ログ監視や社内データの暗号化を実施する。出口対策は、社外通信の経路の制限・ブロックを実施する。
(4)業務遂行において必要な倫理、社会の持続性
倫理の観点に関する要件は、常に公共の安全と福利を第一に考えることである。安全性を損なうことやデータ不正・改ざんをすることは決して行わない。
持続性の観点に関する要件は、省エネ・省資源化を図ることである。例えば、受発注者間のやり取りを情報共有システムで行うことでペーパーレス化を図り、紙消費量を減らすことや、建設作業の効率化を進めCO2を削減するなど環境負荷軽減に留意する。以上