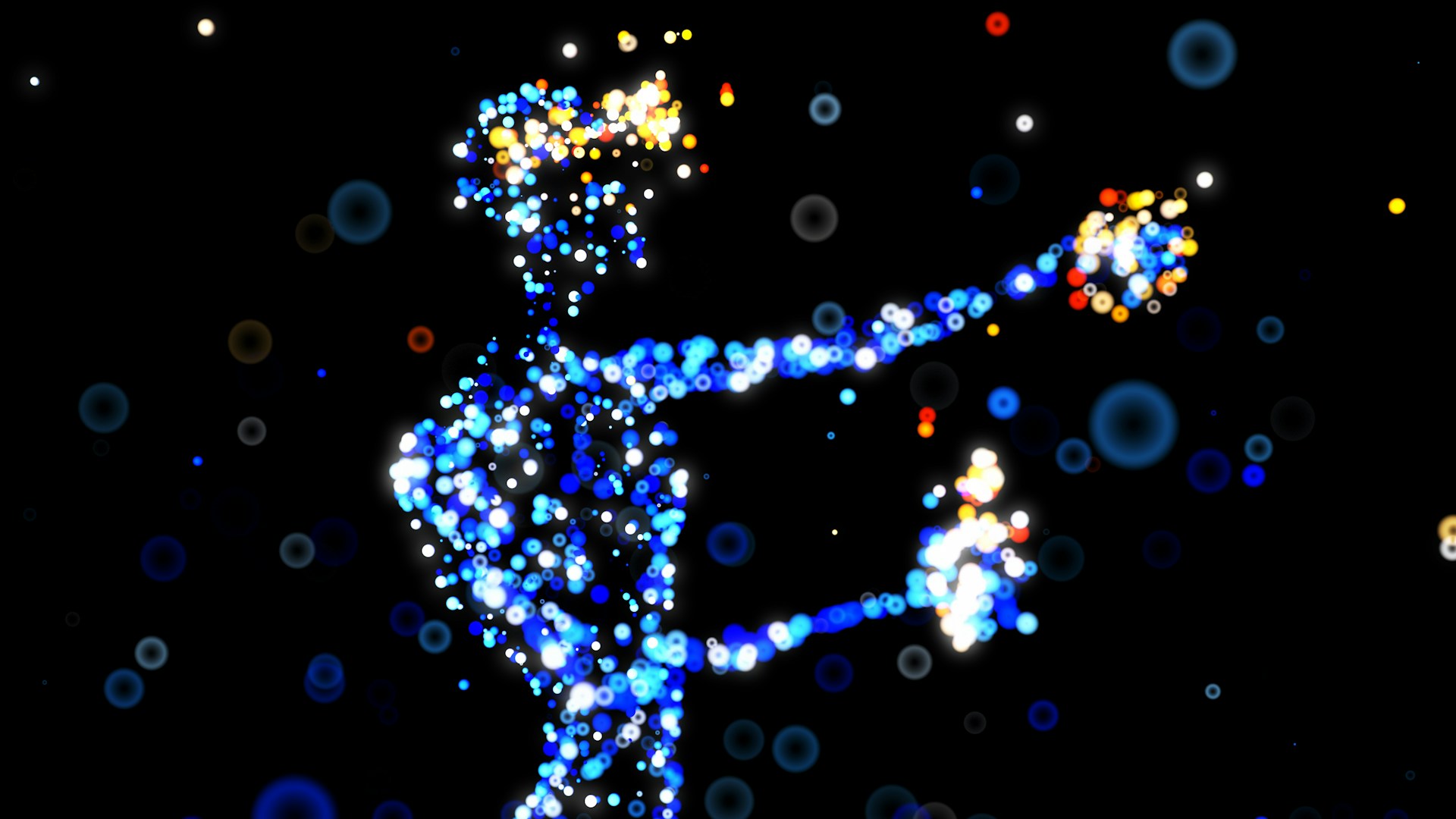添削LIVE
【 技術士 二次試験対策 】
初代複合問題「復旧・復興×DX」
本日は、私のGWのほほん日記は書きません。いきなり添削スタートです。なぜかと言えば、疾風怒濤の4連投だからです。さらに、これからの基本となりうる初代複合問題「復旧・復興×DX」を完成まで一挙にお届けします。複合問題は、どっちで書けば良いんだよという感じで混乱の極みです。両方を満たすとなると記述もメチャクチャハードルが上がります。そんな問題に四苦八苦しないよう、準備をしましょう。何事も準備をしたものが勝つのです!それでは、早速論文を見ていきましょう。
「復旧・復興×DX」 初稿
1.多面的な観点からの課題
(1)コスト面の観点から、財源が確保できないなか で、いかに実施するか。①
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって、税 収が不足する。一方、社会保障費は年々増加している。 財源は確保できておらず、子供たち世代に負担を先送 りし続けている②。そのため、あらゆる事業でコスト 低減を図っていく必要がある③。
① 見出しが長すぎます。見出しは、それを見てどんな内容かすぐ分かるように端的に書きましょう。これは見出しですので、本文中に観点・課題は必要です。また、課題は解決するための行動を含みます。「いかに実施するか」では解決するための行動がなく課題になっていません。いかに実施するのかを問われているのですよ。課題設定を見直しましょう。
② なぜ子供たち世代に負担を先送りし続けているのか説明がありません。国債や地方債の発行のことを言っているのでしょうか。唐突です。
③ 災害の復旧復興あるいはDXとの関係が分かりません。要領が得られないだけでなく、ただの一般論に見えます。「技術者の立場として」という問題の条件を満たしていません。
(2)技術面の観点から、大規模災害発生後の復旧・ 復興までの取組でいかにDXを活用するか④。
建設産業は「地域の担い手」として⑤、災害時には最前線で地域社会の安全・安心の確保を支える役割⑥を担っている。そのため、災害発生時は生活インフラ がなく、天候の急変等による2次災害の危険がある 中でも、現地で緊急対応工事を行うことになるため、 安全衛生の確保が不可欠である⑦。このような状況 の中、迅速な復旧・復興に向けて、急速に進展する DXをいかに活用するかは重要な課題⑧である。
④ ①と同様。また、課題も「いかにDXを活用するか」としていますが、それを問われています。
⑤ 産業が担い手という表現に違和感があります。また、地域の担い手も何なのか分かりません。
⑥ 確保を支えるという表現に違和感があります。単純に「安全・安心を確保する役割」で良いのではありませんか。
⑦ 「そのため、・・・なるため、・・・」と理由が連続しています。一文が長すぎて、非常に分かりづらいです。「危険がある中でも工事を行うことになる」との主張には賛同できません。危険があるからそれを除外するために安全衛生を確保するのですよね。危険な中でも作業しなければいけないから、安全を確保するは似て非なる主張です。
⑧ 脈絡がありません。いきなりDXの活用だと述べても、誰も納得することはできません。DXが求められる背景を書きましょう。ただし、これを修正しても、そもそも①のとおり課題に問題があります。課題設定を見直しましょう。
(3)人材面の観点から、いかに人材不足の中で実施するか。⑨
我が国の総人口は減少傾向にあり、諸外国と比べて 出生率も低い水準にある。少子化や過去の批判的な 報道等による負のイメージ⑩より、今後も建設業に携 わる人材も減っていく恐れがある⑪。このような状況 で、いかに実施するかが課題である。
⑨ ①と同様。
⑩ どういうことでしょうか。
⑪ 今後もとありますが、現状が説明されていません。また、これも③と同様。
- 課題はすべて見直しましょう。技術的な側面からもっと踏み込んだ課題設定が求められます。無人化技術の普及促進、オープンデータ化など復旧やDXに関連するものを検討しましょう。また、課題のパラグラフは、現状→問題点→必要性→結論(観点・課題)の順で書くと分かりやすく構成することができます。
2.最も重要な課題と解決策
(1)最も重量な課題
上記のうち、「大規模災害発生後の復旧・復興まで の取組でいかにDXを活用するか」を最も重要な課題に挙げ、以下に解決策を述べる。⑫
⑫ 選択理由も書くと良いでしょう。
1)ドローンを活用した点検・測慮⑬
復旧に必要な情報を効率的に取得するために、ドロ ーンで構造物を点検する。橋梁や構造物の外壁など、 仮設足場を設置し点検者が目視点検を行う必要がなく、 早期に正確な点検が可能になる⑭。また、レーザー測量や写真測量も実施することで⑮地形の3Dデータ作成も可能となる⑯。そのため、労働者の安全衛生確保につながる⑰。
⑬ →「測量」
⑭ ドローンで点検すると言っているので、このような説明は不要です。どのようにドローンを使って点検をするのかを具体的に述べましょう。
⑮ 点群データを取得するステップも必要だと思います。
⑯ 3Dデータを作成するのではなく、3Dモデルを作成するのではありませんか。
⑰ 3Dデータを作成可能になるとなぜ安全衛生につながるのですか。UAVを用いることで、安全に点検できるのであり、3Dモデリングにより設計検討が容易になるといった関係ではありませんか。整理整頓しましょう。
2)BIM/CIMによる施工計画策定
BIM/CIMを用いて施工計画を行うことで、全体 を立体的に把握することが可能となり、位置関係や 干渉等を視覚的に確認しながら計画を検討できる⑰。 測量した3DデータをBIM/CIMに取り組むことで、 周辺の被災状況の影響を3次元的に把握することができ、より実情に近く、安全性を確保した施工計画 検討が可能となる⑱。
⑱ 「・・・施工計画を行うことで、・・・計画を検討できる」とねじれています。また、何の位置関係ですか。何を把握するのですか。説明不足です。解決策は、目的→やること→具体例といった構成が分かりやすく書けます。→「構造物を立体的に把握し、部材の位置関係や干渉等を視覚的に確認するため、BIM/CIMを用いて施工計画を策定する。具体的には、・・・」
⑰ 前段と同じようなことを述べています。また、ここは解決策のパラグラフなので、可能性を示すのではなく、解決策を示しましょう。⑯のとおり、後半パートは、具体例として書くと良いでしょう。3Dモデル化をするとなぜ安全性を確保した施工計画が検討できるのかを具体例を用いて説明する必要があります。技術力を示すのは、この具体例の内容が重要になります。
3)ICTを活用した自動化施工
ICTを活用した建設機械の自動化や遠隔施工を実施することで、2次災害を防ぎながら復旧を進める。 例えば、BIM/CIMデータやGPSと連携する⑱ことで、掘削・盛土範囲を機械が自動で判断し、工事を 進める⑲。重機オペレーターが不要となり、24時間 施工が可能となる⑳。
⑱ 何を連携するのですか。
⑲ どのような工事なのか説明しないで、いきなり掘削・盛土範囲と言われても唐突で理解できません。前段の例示なので、2次災害を防ぐ復旧工事である必要があります。
⑳ モニタリングする人なども不要なのでしょうか。また、労務手配と周辺環境が許せば、自動でなくても24時間施工可能ではありませんか。これは、波及効果として書いているのですかね。自動化の目的が安全な復旧なのか、迅速な復旧なのかよく分かりません。
4)3Dプリンタによる仮設住宅建設
3Dプリンタを用いて、仮設住宅を建設する。耐震性に優れる鉄筋コンクリート造の住宅を建設することが可能であるため、復興後も長期に渡って居住が可能である。また、作業員が不要であり、建設コストも安価に抑えることができる。㉑
㉑ これも最初に目的を明確化した方が良いです。
3.新たに生じるリスクと対策
(1)リスク
DXが浸透していくと、原理原則を理解せずとも対 策を実施することが可能となる。自分で計算する㉒機会などが減少し、若手技術者の技術力低下するリスクがある。
㉒ 計算に限らないので、「考える」ですかね。
(2)対策
資格制度や教育制度を充実させる。また、キャリア アップシステム㉓やものづくりマイスター制度㉔などを 活用し、技術力の向上を図っていく。
㉓ キャリアップシステムは、建設業の技能者の資格や就業履歴を登録・蓄積するシステムです。技術力を高める教育システムではありません。
㉔ 「また」とありますが、ものづくりマイスター制度も若年技能者の育成を図る制度であり、教育制度の一種ではありませんか。さらに、これらは、技能者を対象としていますから、リスクと感じているのは技術者ではなく、技能者の技能低下が言いたいことなのでしょうか。
4.必要となる要件と留意点
常に公益を最優先に取り組む㉕。さらに、構築して㉖終わりではなく、維持管理を続けて常に安全な状態を維持することが必要な要件であり、そのような取り組みを継続できるように留意する。㉗以上
㉕ 意気込みではなく要件を書きましょう。→「・・・取り組むことが要件である」
㉖ 何を構築するのですか。
㉗ 問題は2つの観点から解答を求めています。一つは倫理、もう一つは持続性です。どれがどれなのか明確にしましょう。
「復旧・復興×DX」 チェックバック①
1.多面的な観点からの課題
(1)新技術の活用
建設産業は、災害時に最前線で地域社会の安全・安心を確保する役割を担っている①。災害復旧工事では、施工が困難な箇所での作業を余技なく②されるなど、通常の建設工事と比べても、作業の安全を確保することが難しい面がある③。よって、安全面の観点からいかに安全性の向上に資する新技術を活用するかが課題である④。
① 抽象的で分かりづらいです。具体的に述べてよいと思います。→「建設業は、災害時に最前線で復旧・復興を行う役割を担っている」
② →「余儀なく」
施工が困難なのに作業させるのはいかがなものでしょうか。違和感があります。例示はない方が分かりやすいと思います。
③ 「比べても」繰り返し表現ではないので「も」はおかしいですね。また、難しい面という表現も、違う側面がないのであれば、「難しい」と端的に表現すべきでしょう。→「災害復旧工事では通常の建設工事と比べて、作業の安全を確保することが難しい」
④ 「安全面の観点から安全性の向上」では、観点と課題が重複しているように見えます。また、背景で、新技術の説明が一切ないにもかかわらず、課題で突然出てきても腑に落ちません。例えば、背景でICT技術の発展などに触れると良いでしょう。
(2)デジタル技術の導入
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって、税収が不足する⑤。一方、社会保障費は年々増加している⑥。しかし、デジタル技術の導入には、費用がかかる⑦。よって、コスト面の観点から、いかにデジタル技術を導入するかが⑧課題である。
⑤ 不足するかどうか歳出予算次第ではありませんか。
⑥ 歳入が減少、歳出が増加といったこの2つの状況を説明したうえで、⑤の不足が理解されます。説明の順番がおかしいですね。
⑦ 「しかし」とありますが、何に対する逆接なのでしょうか。また、イニシャルコストはかかりますが、省力化できるわけですから全体コストは下がるのではないでしょうか。イニシャルコストが用意できないから、資金調達手法(PFIや地方債の拡充?)を問題視ているのですかね。費用がかかるのは当たり前ですから、もっと何を問題視しているのかを明確にしましょう。
⑧ そもそも題意は、どうやってDX化を図るかを聞いているのですから、デジタル技術をどうやって導入するか(DX化とほぼ同義)を課題にしても解答になっていないと思います。これでは、「おいしい料理どうやって作りますか」と聞かれているのに、「おいしく作ります」と答えているようなものです。
(3)人材の確保
我が国の総人口は減少傾向にあり、諸外国と比べて出生率も低い水準にある。建設業就業者数も1997年をピークに減少が続いている⑨。そのため、DX活用により⑩、生産性を向上させる必要がある。そこで、DXを活用できる技術を持った人材が必要である。よって、人材面の観点からいかにDXを活用できる人材を確保するかが課題である⑪。
⑨ 出生率が低いことを説明する必要がありますかね。ここで言いたいことは、建設業の就業者数が減っているということだと思います。スペースが限られているので、端的な表現を心掛けましょう。→「我が国の総人口は減少傾向にあり、建設業就業者数も1997年をピークに減少が続いている」
⑩ 前述の背景のみでは、DX活用という手段が読み取れません。デジタル技術の発展を説明し、その活用の必要性を示したうえで記述しましょう。
⑪ 人材が必要→人材面の観点→人材を確保といった説明になっており、同じことが何度も繰り返されています。例えば、生産性の向上が必要→人材面の観点→デジタル技術を教育といったように、文脈を通して結論に導く構成が求められます。
2.最も重要な課題と解決策
(1)最も重要な課題
公衆の安全を確保することが最優先であるため、上記のうち「いかに安全性の向上に資する新技術を活用するか」を最も重要な課題に選定し、以下に解決策を述べる。
(2)解決策
1)ドローンを活用した点検・測量
復旧に必要な情報を安全に得るために、ドローンで構造物を測量する⑫。具体的には、レーザー測量による点群データの取得により、3Dモデルを作成する⑬。そして、点検結果を3Dモデルに記録する⑭。さらに、作成した3Dモデルを関係者と共有することで、設計検討や工事にも活用することが可能⑮となる。
⑫ 見出しには点検・測量とありますし、前述にも必要な情報とあります。よって、測量のみとすることに違和感があります。
⑬ 何の3Dモデルを作成するのですか。なぜ3Dモデルを作成するのですか。
⑭ 点検結果とは何ですか。事前に調査したもの?被害状況?説明不足です。また、これもなぜ記録するのですか。行動の目的が不明です。
⑮ これも関係者とはだれか、どのように活用されるのか、なぜ3Dモデルでなのか、といった説明がなく、「具体的には」とはありますが抽象的な説明です。
2)BIM/CIMによる施工計画
構造物を立体的に把握し、部材の位置関係や干渉等を視覚的に確認するため、BIM/CIMを用いて施工計画⑯を策定する。具体的には、周辺の被災状況を再現した3Dモデルで、クレーンやヤードの配置を検討する。これより、より実情に近く安全性を確保した施工計画が策定できる。
⑯ 施工計画ですとBIM/CIMのそもそもの活用方法だと思いますので、ここは題意に即するためにも「復興計画」としてはいかがでしょうか。
3)ICTを活用した自動化施工や遠隔操作
ICT建機による建設機械の自動化や遠隔操作により、2次災害を防ぎながら復旧工事を行う。具体的には、崩落した斜面の切土工事でバックホウやダンプを遠隔で操作することで、オペレーターの安全を確保する。
4)AIによる損傷個所の抽出
写真画像からAIを用いて危険な損傷個所を抽出する⑰。具体的には、人が容易にアクセスし辛い箇所をドローンで写真を撮影し⑱、その画像からAIで損傷の激しい箇所を抽出する⑲。この技術により、点検者は高所や狭所などの点検業務を最小限にすることができる⑳。
3.新たに生じるリスクと対策
(1)リスク
DXが浸透していくと、原理原則を理解せずとも対策を実施することが可能となる。自分で考える機会などが減少し、若手技術者の技術力が低下するリスクがある。
(2)対策
教育制度の充実や資格制度を積極的な活用、資格取得の義務化を図る㉑。
㉑ 「資格制度を積極的な活用」→「資格制度の積極的な活用」
資格は活用するのですか、義務化するのですか、2つを同列で提案することに違和感があります。
また、もう少し具体的に述べた方がよいです。技術力のアピールは、具体性と心得てください。
※リスク、対策といった小見出しは不要です。このスペースでもっと詳細を説明しましょう。
4.必要となる要件と留意点
技術者倫理の観点から必要になる要件は、社会全体における公益を確保する視点㉒と、安全・健康・福利の優先である。社会持続性の観点から必要になる要件は、環境・経済・社会における負の影響を低減し、安全・安心な社会資本ストックを構築し維持し続ける視点を持つことである。業務遂行の各段階で、常にこれらを意識するように留意する。 以上
㉒ 要件の説明を「視点」は不要。→「こと」
「復旧・復興×DX」 チェックバック②
1.多面的な観点からの課題
(1)新技術の活用
建設産業は、災害時に最前線で復旧・復興を行う役割を担っている①。災害復旧工事では通常の建設工事と比べて、作業の安全を確保することが難しい。そのため、急速に発展するICT技術の展開が急務である②。よって、安全面の観点からいかに新技術③を活用するかが課題である。
① この記述の意図が分かりません。安全を確保することが難しいとする現状を述べましょう。
② 安全確保とICT技術との関係性が示されておらず、急務であるとする理由が分かりません。飛躍しており、順を追った説明が必要です。
③ 新技術では、その範囲が広すぎます。もう少し、絞り込んだ方が良いでしょう。この場合でイメージされる新技術は、施工の無人化とかですかね。
(2)ハードの整備
我が国の社会保障費は年々増加している。しかし、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって、税収が不足している④。一方で、DXを導入するためには、ハード整備にコストがかかる⑤。そのため、ランニングコストを考慮した全体コストの評価⑥が必要である。よって、コスト面の観点から、いかにハードの整備を進めるかが課題⑦である。
④ こんなにスペースを使って、財務状況を説明する必要はないと思います。もっと、端的に表現しましょう。→「近年、少子高齢化や人口減少により、地方の財政は逼迫している。」
⑤ DXの導入コストなのか、ハード整備のコストなのかよく分かりません。どちらかを焦点化しましょう。
⑥ DXも関係なければ、復旧復興にも関係がないように見えます。
⑦ 前述では、LCC評価が必要としておきながら、ハード整備をどうやって進めるかでは、支離滅裂です。順序だてて説明し、文脈を通しましょう。
(3)デジタル技術の教育
我が国の総人口は減少傾向にあり、建設業就業者数も1997年をピークに減少が続いている。しかし、自然災害は頻発化・激甚化している。そのため、復旧・復興作業の生産性を向上するため⑧、デジタル技術を活用できる体制の構築⑨が必要である。よって、人材面の観点から、いかにデジタル技術の教育を充実させるかが課題である。
⑧ 「そのため、・・・するため」と連続しています。さらに、災害が頻発化・激甚化しているとなぜ生産性の向上が必要なのですか。飛躍しており、説明不足です。
⑨ 結論は教育の充実ですし、前述は人手不足のように見えます。しかし、ここへきて急に体制の話になっています。これもまた、文脈が通っておらず、思いの主張を思うまま書いているように見え、整理整頓ができていないといった印象を受けます。
2.最も重要な課題と解決策
(1)最も重要な課題
公衆の安全を確保することが最優先であるため、上記のうち「いかに安全性の向上に資する新技術を活用するか」を最も重要な課題に選定し、以下に解決策を述べる。
(2)解決策
1)ドローンによる被害状況の情報収集
復旧に必要な情報を安全に得るために、ドローンで構造物や地形の被害状況を確認・記録する。具体的には、斜面崩壊が起きた橋梁をドローンで写真撮影し、被害の範囲を確認する。また、橋梁の損傷状況を点検する⑩。さらに、点群データの取得により、3Dモデルを作成し、被害状況や点検結果を記録することで、設計者や施工者と情報共有の迅速化も可能となる⑪。
⑩ 類似した内容が繰り返されているので、まとめてしまいましょう。→「被害の範囲及び損傷状況を確認する。」
⑪ 可能性ではなく、やることとして書きましょう(「可能となる」ではなく、「迅速化を図る」)。また、ドローンの写真撮影だけでは、点群データを取得することはできないと思います(写真解析を説明)。さらに、迅速な情報共有が目的なのに、なぜ、わざわざ3Dモデルを作成するのかも分かりません。手段の目的をきちんと理解したうえで、整理整頓しましょう。
2)BIM/CIMによる復興計画
構造物を立体的に把握し、部材の位置関係や干渉等を視覚的に確認するため、BIM/CIMを用いて復興計画⑫を策定する。具体的には、周辺の被災状況を再現した3Dモデルで、クレーンやヤードの配置を検討する。これより、より実情に近く安全性を確保した施工計画が策定できる⑬。
⑫ 修正いただいていますが、具体例は、施工計画のままになっており不整合です。復興計画が難しいようであれば、「多角的に復旧手法を検討する」なども考えられます。また、手段と目的が逆ではありませんか。確認するために計画を作成するのではなく、計画を策定するために視覚的に確認するのではないでしょうか。さらに、立体的に、視覚的にと似たような説明が繰り返されています。整理整頓が必要です。例えば、以下のような表現が考えられます。
→「多角的かつ詳細に復旧手法を検討するため、BIM/CIMを用いて設計・施工を行う。」
⑬ 配置を検討するだけなら、平面図でできます。3Dモデルの特徴を踏まえた検討手法を説明すべきです。
3)ICTを活用した自動化施工や遠隔操作
ICT建機による建設機械⑭の自動化や遠隔操作により、2次災害を防ぎながら復旧工事を行う。具体的には、崩落した斜面の切土工事でバックホウやダンプを遠隔で操作することで、オペレーターの安全を確保⑮する。
⑭ 重複表現です。
⑮ シチュエーションは具体的ですが、ICT施工を実施するための具体的方法なども記載すると技術力アピールにつながると思います(一般論を脱し切れていない)。前述のBIMで作成されたデータをICT建機に入力&出来形管理といった流れを説明してはどうでしょうか。
4)AIによる損傷個所の抽出
危険な損傷個所を素早く把握するため、AI技術を活用し写真画像から損傷個所を自動で検出する。具体的には、人が容易にアクセスし辛い箇所をドローンで撮影し、その画像をリアルタイムで解析することで、危険な箇所を抽出する。また、高所や狭所などの点検が容易になるため、省力化といった波及効果がある。
3.新たに生じるリスクと対策
DXが浸透していくと、原理原則を理解せずとも対策を実施することが可能となる。自分で考える機会などが減少し、若手技術者の技術力が低下するリスクがある。対策として、熟練技術者とのOJT教育や研修制度の充実化、資格制度の積極的な活用により、技術力の向上を図る。
4.必要となる要件と留意点
技術者倫理の観点から必要になる要件は、社会全体における公益を確保することと、安全・健康・福利の優先である。社会持続性の観点から必要になる要件は、環境・経済・社会における負の影響を低減し、安全・安心な社会資本ストックを構築し維持し続ける視点を持つことである。業務遂行の各段階で、常にこれらを意識するように留意する。 以上
「復旧・復興×DX」 完成
1.多面的な観点からの課題
(1)建設作業プロセスの無人化
建設現場の作業では、未だマンパワーに依存している。一方、災害復旧工事では通常の建設工事と比べて、作業の安全を確保することが難しい。よって、安全面の観点から、いかに建設作業のプロセスを無人化するかが課題である。
(2)インフラ情報のアーカイブス化
大規模災害では、公共施設等でも被害が発生している。一部の自治体では、情報が紙媒体で保管されている。そのため、被災により焼失し、復旧の妨げになっている。被災からの復旧を迅速に行うためには、インフラ情報をデジタル化し、災害時でも活用できるシステムづくりが必要である。よって、冗長性の観点から、いかに情報のアーカイブス化を進めるかが課題である。
(3)デジタル技術の教育
近年の労働力不足を補うためには、IT技術の活用は欠かせない。また、災害時は特に人手が不足するため、IT技術が果たす役割は一層大きくなる。一方、IT技術の専門性は高度化し、十分な知識がないと技術の進歩に対応できない。よって、人材面の観点から、いかにデジタル技術の教育を進めるかが課題である。
2.最も重要な課題と解決策
(1)最も重要な課題
作業中の安全を確保することが最優先であるため、上記のうち「建設作業プロセスの無人化」を最も重要な課題に選定し、以下に解決策を述べる。
(2)解決策
1)ドローンによる被害状況の情報収集
復旧に必要な情報を安全に得るために、ドローンで構造物や地形の被害状況を確認・記録する。具体的には、斜面崩壊が起きた橋梁をドローンで写真撮影を行い、被害の範囲及び損傷状況を把握する。また、ドローンレーザー測量により取得した点群データから3次元モデルを作成する。このモデルを用いて崩落部の断面を作成し、災害査定を行う。これより、不安定な斜面での測量業務を無くし、測量士の安全を確保する。
2)ロボットによる被害状況の情報収集
被災した建造物の被害状況を安全に把握するため、レスキューロボットを導入する。具体的には、カメラを搭載した四足歩行のロボットを遠隔操作し建造物内部の写真を撮影する。その写真をARソフトで加工し、柱の傾きなどを計測することで、建造物の安定性を評価する。また、作業の安全確保のみならず、人が入れない狭い場所での調査も可能になる。
3)ICTを活用した建設機械の遠隔操作や自動化
建設機械遠隔操作や自動化により、2次災害を防ぎながら復旧工事を行う。具体的には、崩落した斜面の復旧工事で、ICT建機を遠隔で操作し切土作業を行いオペレーターの安全を確保する。さらに、ICT建機に、点群データより作成した3次元データを入力する。これより、切土範囲を自動で調整可能となり、作業効率の向上といった波及効果も生じる。
4)AIによる損傷個所の抽出
危険な損傷個所を素早く把握するため、AI技術を活用し写真画像から損傷個所を自動で検出する。具体的には、人が容易にアクセスし辛い箇所をドローンで撮影し、その画像をリアルタイムで解析することで、危険な箇所を抽出する。また、足場の設置や打音検査が不要となり、省力化といった波及効果がある。
3.新たに生じるリスクと対策
DXが浸透していくと、原理原則を理解せずとも対策を実施することが可能となる。自分で考える機会などが減少し、若手技術者の技術力が低下するリスクがある。対策として、熟練技術者とのOJT教育や研修制度の充実化、資格制度の積極的な活用により、技術力の向上を図る。
4.必要となる要件と留意点
技術者倫理の観点から必要になる要件は、社会全体における公益を確保することと、安全・健康・福利の優先である。社会持続性の観点から必要になる要件は、環境・経済・社会における負の影響を低減し、安全・安心な社会資本ストックを構築し維持し続ける視点を持つことである。業務遂行の各段階で、常にこれらを意識するように留意する。 以上