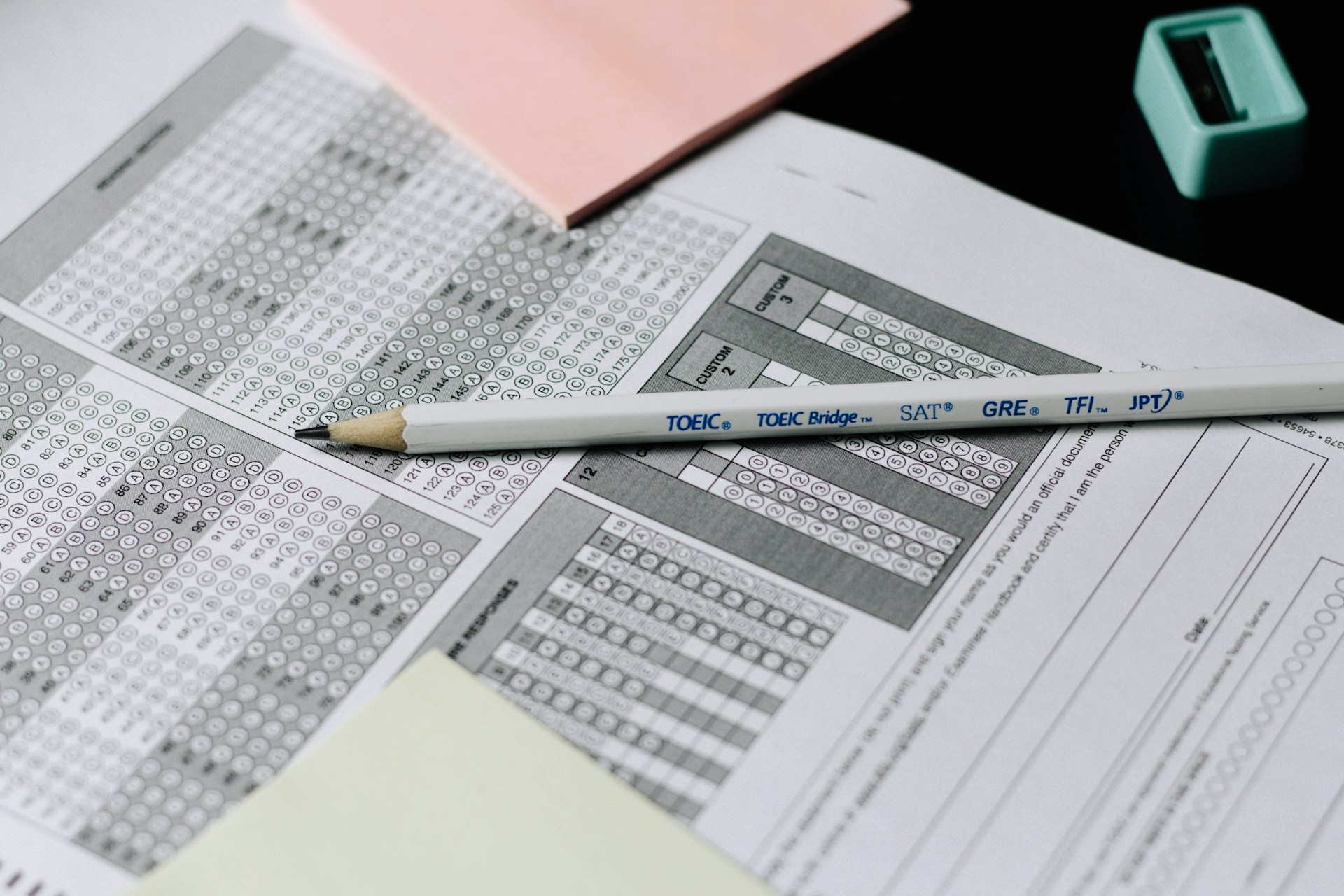添削LIVE
【 技術士 二次試験対策 】
技術士の思考を身につけよう
試験をようやく終え、今週末は心身ともにリフレッシュでした方も多いのではないでしょうか。ゆっくりとした時間を過ごせることの価値を再認識したのではないでしょうか。やはり、ウィークデイがあるからウィークエンドが楽しいのであり、辛い試験勉強を乗り越えたからこそ、今の時間の素晴らしさが人一倍なのでしょう。
そんな、ゆっくりとした時間を過ごすのに最適なのは読書です。私も、少し余裕が出てきたので、読書にどっぷりつかりたいと考えています。あれもこれも読みたいものばかりで、時間はいくらあっても足りません。良い文章の書き方や、適切なコミュニケーションを学ぶのに読書ほど最適なものはありません。
でも、試験も終わったのに、また勉強かよ…と沈痛な面持ちになってもいけませんので、今は気軽に勉強をあまり意識せず読める本が良いと思います。それでいて、技術士の二次試験に役立つという、一挙両得の書籍をご案内しましょう。
本サイトでも、ちょくちょくPRさせてもらっている「能力を最大化するたった3つの技術 ~技術士思考~ 」をこの時期に読んでいただければ、技術士の考えや口頭試験対策を身につけることができます。焦燥感が霧散したこの時期だからこそ、あるいは筆記試験を経験したからこそ、ぜひ手に取ってほしいのです(本書の紹介ページはコチラ)。
このような時期であるがゆえに、本書にある記述内容をみるみる吸収できると思います。内容は、口頭試験にも役立ちますし、これから技術士になるみなさんにも大いに役立つものになっています。本書にある思考力が身に付けば、技術士ライフはイージーモードに突入します。
本書は、サクッと読める、それでいて技術者にお役立ちの情報が満載です。私は、「技術士養成講座(至高の合格マニュアル)」も販売させていただいておりますが、多くの人に読んでもらいたいのは、今回紹介させていただいた本書なのです。
合格のテクニックより、技術士としてのテクニックを身につけてほしいと考えるからです。テクニックと述べましたが、本書のタイトルにもあるように「技術士の思考」と言い換えることもできます。この思考を身につければ、口頭試験においても一貫性のある回答が自然とできるようになります。
また、これから筆記試験を受けたいという人も、記述のテクニックだけでなく、試験で求められるコミュニケーション能力を発揮するための秘訣もしたためられているので、技術士を目指す人、あるいはすでに技術士である人にもお勧めしたいのです。
ご自身の考えを整理する上でも有効ですし、技術者版ライフハック的な要素もあるので、新たな気づきをえることもあるでしょう。この機会にぜひご一読ください。
 |
新品価格 |
![]()
復元論文フルセット第2弾 選択科目Ⅱ
本日の添削LIVEは、令和7年度 建設部門 都市及び地方計画 の復元論文第2弾をお届けします。第2弾では、選択科目Ⅱをお届けします。選択科目Ⅱー1は「Park-PFI」、選択科目Ⅱー2は「3D都市モデル」です。Park-PFIは鉄板と言えますが、興味深いのは3D都市モデルを活用した基本構想の策定です。ツールとしては何度も登場する3D都市モデルですが、問題そのものになっていますね。デジタル技術は、これからも要チェックのトピックです。それでは、早速論文を見てみましょう。
選択科目Ⅱー1 「Park-PFI」
Ⅱー1-4 都市公園法に基づく公募設置管理制度(Park-PFI)について、制度の内容をのべるとともに、従来の設置管理許可(公募設置管理制度に基づかない通常の手続きの設置管理許可)には無い公募設置管理制度の法令上の特例措置を複数挙げ、それぞれの事業者にとってのメリットを説明せよ。
(1) Park-PFI制度の概要
都市公園法に基づき、都市公園に対して、カフェ等の公募対象公園施設(収益施設)と園路、広場等の特定公園施設を併せて設置、管理、運営する者を公募により選定する制度①。公園管理者は管理コストを削減しながら質の高い公園整備が可能となる②。公園利用者は質の高いサービスが受けられる③。
① 主語がありません。箇条書きでないので、体言止めは好ましくありません。「都市公園に対して」との表現も違和感があります。「都市公園において」、「都市公園内に」などですかね。→「Park-PFIは、都市公園法に基づき、都市公園内にカフェなどの収益施設と園路・広場などの特定公園施設を一体的に設置・管理・運営する事業者を、公募により選定する制度である」
② 効果だけでなく、収益の一部を活用して公共施設の整備・維持管理を行うといったスキームも記述する必要があると思います。
③ これと②は、それぞれの効果を並列で書くのではなく、財政負担軽減とサービス向上を両立できることを特徴として書いた方がより良いと考えます。
(2) 法令上の特例措置
①設置管理期間の特例
設置管理期間④を最長20 年とできる。
事業者メリット:収益施設を長期間運営できるため、中長期を見据えた安定した運営、設備投資が可能⑤。
④ →「設置管理許可期間」
⑤ 安定した運営は経営によりますし、設備投資が可能かどうかは回収を度外視すれば従来方式でも可能です。よって、投資を回収できる可能性が高まることがメリットではありませんか。
②建蔽率の特例 ※本番は竹冠にするミス
収益施設について、標準2% であるものが最大12%となる⑥。
事業者メリット:収益を上げられる床面積が増加するため、事業収支が向上する⑦。
⑥ 見出しには、あるもののこれでは何が12%になるのか分かりません。主語を書きましょう。
⑦ 床面積が増えるからと言って、単純に収益が上がるという理屈は腑に落ちません。収益向上の“可能性”を高めるにすぎないのではないでしょうか。あるいは、企画力・設計力・運営力といったノウハウを生かしやすいといったことはメリットではありませんか。
③占用物件の特例
広告塔⑧、自転車駐輪場等を公園内に占用できる。
事業者メリット:広告塔の収益により事業収支を向上できるとともに利用者の利便性を向上できる⑨。
※本番は最後まで 以上
⑧ これには条件があります。地域における催し物に関する情報を提供することが主たる目的である看板、広告塔が占用許可の対象です。
⑨ 利用者の利便性向上がなぜ事業者のメリットなのでしょうか。また、なぜ広告塔の収益により利用者の利便性が向上するのかも分かりません。
選択科目Ⅱー2 「3D都市モデル」
Ⅱー2-1 ある大都市の地方公共団体において、都市の玄関にふさわしい空間が不足している駅周辺地域の駅前広場及び道路空間を対象として、都市空間再構築のための基本構想を作成することとなり、この検討に当たり、関係者との円滑な合意形成を図るため、3D都市モデルを活用することとなった。
あなたが、3D都市モデルを活用した基本構想を作成する業務の担当責任者として、下記の内容について記述せよ。
(1)あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
(2)3D都市モデルを活用して都市空間再構築のための基本構想を作成するまでの業務手順を列挙し、それぞれの段階で留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。
(1) 調査、検討すべき事項とその内容
①地域の状況①:地域の歴史的な形成過程、土地・建物の所有管理状況、産業の状況、交通動向を調査する②。既存のアンケート等の資料も有無を含めて調査する③。交通の将来予測も整理する④。
① さすがに抽象的すぎます。状況把握とはすなわち調査事項なわけですから、もっと細分化する必要があります。
② ①のとおり、細分化する必要があります。3D都市モデルを活用することを踏まえると、現況空間構成の把握、人流・交通・滞留状況の分析、災害リスク・バリアフリー・景観等の評価などが考えられます。
③ アンケートを行うのではなく、過去データを調べるということですか。記述の意図と目的がよく分かりません。
④ 予測を整理とはどのような行動なのか分かりません。また、これは前述にある交通動向に含まれるのではありませんか。とにかく、このパラグラフは、バラバラな印象を受け、項目(調査・検討事項)としてまとまりがありません。
②上位関連計画:都市計画マスタープラン、立地適正化計画、地域公共交通計画、都市再生整備計画等の上位関連計画を整理する⑤。
⑤ 問われているのは、調査・検討事項です。文末は「調査する」ですね。
③関連組織:交通事業者の協議会等、既存の組織体を調査する⑥。
⑥ 調査目的がよく分かりません。調整対象者を把握するためなら、タスクとして些末に感じます。
(2) 業務を進める手順及び留意点、工夫点
①基礎データの整理
調査した地域の状況等の基礎データを整理する⑦。3D モデルに活用する上で不足する、人流データ等の詳細なデータは民間から受領する工夫をする⑧。また既存のアンケート等の定性的データが存在する場合は、位置情報を元に3D モデル上に位置づける工夫をする⑨。
⑦ 基礎データの整理とは何を行うのでしょうか。問題で最も重要な要素は、3D都市モデルを活用することですから、データを収集したら駅前広場・道路空間の3Dモデルを構築することがここですべき、整理なのではありませんか。最も大事な要素が欠如しています。
⑧ 入手の工夫であり、整理の工夫点になっていません。そもそも、「ないものは民間から入手」といった記述は工夫点と言えるのか、また技術的な内容とは言えず技術士論文の工夫点としてふさわしいか疑義があります。3Dモデルを構築することが前提なのですから、3D都市モデルに関連した工夫点であることが望まれます(LOD選定(詳細度)、属性情報の付与など)
⑨ 行動の目的も分からなければ、なぜ工夫点と考えたのかも分かりません。さらに、位置情報とは何を指しているのでしょうか。回答者の居住地ですか?説明不足です。意見やニーズの分布傾向を可視化するといったことですかね。とにかく内容が分かりづらく、工夫点なのか判断できません。
②課題の抽出
整理した基礎データを元に構想作成の上での課題を抽出する⑩。データを重ね合わせ、分野別に色分けを行う等、視覚的に分かりやすくする工夫をする⑪。
⑩ これも3D都市モデルを活用するといった視点が欠如しています。また、構想作成上の課題ではなく、都市空間再構築に向けての課題ではありませんか。これらの課題を整理する上でも、次なるステップは、空間解析(GIS・シミュレーションにより人流・交通・災害等の分析)などが必要なのではありませんか。
⑪ データの重ね合わせというと2次元でのレイヤーということですかね。そうなると、3D都市モデルの特徴が生かされておらず、題意に即していないと思います。
③再構築の方向性、目標の検討
再構築の方向性及び目標を検討する。将来予測を元に複数パターンを検討し、比較できるよう工夫する⑫。既存計画における将来整備方針と整合するように留意する⑬。
⑫ 将来予測とはなんですか。前のステップでシミュレーション等をしているのなら分かりますが、そもそも将来予測ステップがありません。しかも、何を比較するのかも分かりません。説明不足です。
⑬ 一般的な留意点であり、PLATEAU VIEW等を活用など、もっと3D都市モデルをフィーチャーすべきです。
④具体策の整理
目標の実現のための具体的な方策を整理する。方策の実現に向けたステップを3D モデル上で時系列に示す等の工夫をする⑭。市民への説明会やwebでのアンケート等を行い、市民意見の反映を行うことに留意⑮する。 ⑯
⑭ やっと3D都市モデルを活用した工夫点が出てきました。これはとても良いです。
⑮ これは留意点というより、合意形成という一つの手順であるように感じます。
⑯ 問題には基本構想を作成するまでの手順とありますので、最後のタスクとして「基本構想の作成」という手順の記載が必要です。
(3) 関係者との調整方策
①庁内他部局
計画策定には都市、交通部局のみならず、企画、産業振興等多くの部局が関連する。そのため定期的に検討会議を開催し意見交換する⑰ことで効率的となる。
⑰ 間違いではありませんが、やはり技術的視点に欠けています。PLATEAU VIEWやWebGISを活用した情報共有環境を構築するなど、技術的示唆に富んだ記述が求められます。
②協議会
計画には交通事業者等を含めた多くの事業者が関連するため、協議会等を活用して協議の場を設ける⑱。データのやり取りが生じると考えられることから、あらかじめデータ利用やセキュリティの考え方についてガイドラインを関係者間で共有しておくことで効率的となる⑲。
⑱ 前項と同じような方策であり、対象者の特性に応じた方策の提案が求められます。
⑲ これはセキュリティが高まるのであって、効率化される理屈が分かりません。
③都市計画審議会、景観審議会等
都市計画審議会、景観審議会等に事前に情報共有し計画、外観の観点で意見を得る⑳。 以上
⑳ 都市計画審議会は、都市計画を定める際に、その内容を調査・審議する機関です。都市計画の変更が伴うのでしょうか。ただのアドバイスをもらうということで、同組織を活用するのはいかがなものでしょうか。