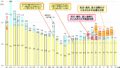添削LIVE
【 技術士 二次試験対策 】
求められる地球温暖化対策
ここ最近の暑さは異常です。国内各所では、気温が40度を超える事態になっています。2018年の埼玉県熊谷市で気象庁観測史上日本歴代最高気温となる41.1℃を記録した時から、10年もしないうちに40度越えは、常態化しつつあります。
昭和生まれのおじさんが抱く夏休みのイメージは、近所のプールに出かけたり、虫取りをしたりと外遊びが中心です。しかし、最近は熱中症アラートが頻発し、こどもたちが外で遊ぶ声もめっきり聞こえなくなりました。
この熱中症アラートも最近よく耳にしますが、運用が始まったのは令和6年4月からです。こんな直近の出来事なのに、毎日のように発表だれる熱中症アラートはすでに生活に溶け込んでいます。このような身近な例は、気温の上昇が急激に変化している証左なのでしょう。
さらに、地球温暖化もたらす大きな影響と言えば、気候変動に伴う災害の激甚化・頻発化です。9月5日から6日に、日本列島を横断した台風15号は、道路冠水や床下浸水だけでなく、突風・竜巻による家屋倒壊などこれまでにはあまり見られなかった被害も確認されています。
もちろん、これら被害を軽減するためにインフラ整備は不可欠ですが、気候変動による影響の拡大スピードは速く、対応が間に合わないのが実情です。そのため、最近では分野横断的に対策を勧めたり、ICT技術を活用したりと奮戦しているものの、一朝一夕に解決できそうもありません。
さらに、このまま地球温暖化が進行すれば、さらなる悪影響の拡大が懸念されることとなり、暑さや災害におびえて暮らさなければならない事態はすぐそこまで来ています。これを抜本的に防止するため、我々技術者は常に1トンでもCO2を削減できないか考える必要があります。
まさに、技術士に求められる「持続可能な社会の実現に貢献すること」に向け、一丸となって取り組む必要があります。現在携わっている仕事でCO2を削減できることはありませんか。積土成山、少しでも構いませんので、我々技術者が先頭を切って範を示す必要があります。
当然ですが、技術士論文・口頭試験でも、持続可能な社会の実現への対応はふんだんに盛り込みましょう。
「第六次環境基本計画」
お久しぶりの添削LIVEは、「第6次環境基本計画」をお届けします。本論文は令和7年度の筆記試験前の練習論文として作成されたものです。このテーマは、令和7年度環境部門において、バッチリ出題されています。投稿者の先見性に驚かされております。もっと、はやく投稿すれば良かったと悔やまれます(反省です)。それでは、ドストライクな予想問題を早速見ていきましょう。
問題:第六次環境基本計画では、「環境・経済・社会の統合的向上の高度化」を図るために、6つの戦略が示されている。それぞれの戦略は、①「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムの構築、②自然資本を基盤とした国土のストックとしての価値の向上、③環境・経済・社会の統合的向上の実践・実装の場としての地域づくり、④「ウェルビーング/高い生活の質」を実感できる安全・安心、かつ、健康で心豊かな暮らしの実現、⑤環境を軸とした戦略的な国際協調の推進による国益と人類の福祉への貢献、である。これらの戦略について以下の問いに答えよ。
(1)核戦略を踏まえて第六次環境基本計画を進めていくうえで、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し、その内容を観点とともに示せ。
(2)前問(1)で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。
(3)専門(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
(4)前問(1)~(3)の業務遂行に当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要な要件を題意に即して述べよ。
1.第六次環境基本計画を推進していくための課題
(1)環境・経済・社会の同時解決(地域の観点)
気候変動や海洋プラスチック汚染、天然資源の確保など世界規模の問題が顕在化している。一方、国内でも環境問題のほか、特に地域での人口減少や少子高齢化、経済の長期停滞など、様々な問題が生じている。
このため、環境に配慮したうえで各種問題を同時に解決する施策や事業を推進し、持続可能な社会を目指していくことが課題①である。
① 課題が何か判然としません。見出しには「同時解決」るすことが課題のように書いてありますが、この文章は同時解決を手段として述べています。その結果、持続可能な社会を目指すことが課題になっています。どちらが言いたいことなのでしょうか。また、「社会を目指す」は目標のように見えます。課題として書くのであれば、「社会の実現」ではありませんか。さらに、背景は、環境問題と社会問題をそれぞれ記述したに過ぎなく、同時に解決する必要性が分かりません。加えて、見出しには「環境・経済・社会」とありますが、経済に関する背景もありません。
なお、観点は見出しだけに記述するのではなく、本文中にも書きましょう。地域の観点という表現もどのような立場なのか分かりません。観点は、課題のジャンルというイメージで書くと良いと思います。→「〇〇の観点から・・・が課題である」※以下すべて同じ。
(2)自然資本の活用(多機能の観点)
高度経済成長期における経済を優先した都市開発などにより、里山や緑地は荒廃・減少し、生物多様性は損失した②。生物多様性の損失は、食料供給、防災、環境教育③など、自然資本が有する多面的機能(生態系サービス)を低下させている④。
このため、自然資本を維持・回復させることにより、生態系サービスの向上を図り、多面的機能を社会に浸透させていくことが課題⑤である。
② 断定してしまうことに違和感があります。完全になくなったわけではないので、「損失が懸念される」くらいにトーンを落としてはいかがでしょうか。
③ 環境教育の目的には、そもそも生物多様性の確保も含めれているのではないでしょうか。要因と結果が逆に見えます。
④ 生態系サービスとは、生物多様性によって提供される自然の恵み(サービス)のことですから、生物多様性が失われれば低下するのは当然ですから、当たり前のことを説明しているように見えます。
⑤ これも課題が何なのか判然としません。見出しは「自然資本の活用」となっていますが、文中では「多面的機能を社会に浸透させていくこと」になっています。不整合です。維持回復したいのか、生態系サービスの向上を図りたいのか、多面的機能を浸透させたいのか、自然資本を活用したいのか、とにかく論点がはっきりしていません。論点を明確にしたうえで、背景を課題に沿った形で解決策に誘導する文脈)で文章を校正しましょう。お勧めしているのは、①現況→②問題点→③必要性→④結論(観点・課題)といった構成です。
(3)環境技術者の確保・育成(人材の観点)
少子高齢化による労働力不足により、特に地方において、環境や社会を取り巻く諸問題に対応できる民間技術者や技術系公務員が不足している⑥。
このため、地方への専門家・アドバイザリー派遣⑦や現場研修を通じたOff-JTを通じて、環境技術の魅力を高め⑧、技術者を確保・育成することが課題である。
⑥ 冗長的な表現です。余計な説明や、一文が長いことが要因だと考えます。→「近年の少子高齢化により、環境に関する技術者が不足している。特に地方都市においては、その傾向が顕著であり、地域の環境課題を解決する上で深刻な障害となっている。」
⑦ アドバイザリーは助言を行うサービスや役割、アドバイザーは助言を行う専門家です。→「アドバイザー派遣」
⑧ ここまで書いてしまうともはや解決策を記述しているに等しいです。不要。
2.最重要課題と理由
1(1)環境・経済・社会の同時解決は、他の課題の基盤⑨となるものであり、最重要課題と考える。解決策は以下のとおり。
⑨ 同時であることはタイミングの話であり、むしろ解決の基盤となるのは、自然資本や人材ではないでしょうか。選択の理由として、腑に落ちません。
(1)再生可能エネルギーの導入の加速化
環境や経済等の同時解決において、エネルギーの安定供給の観点で、再生可能エネルギー施設の導入を推進することが有効である⑩。
このため、国や地方自治体が主体となり再エネ施設を推進していく⑪。具体的には、風力や太陽光の再エネ設備の設置者に対する融資や補助金による支援を拡充していく⑫。また、再エネ施設のリプレースに係る規制緩和⑬や、ペロブスカイト太陽電池など次世代装置の実証試験を行うなどして、エネルギーの地産地消⑭を高め、生活利便性の向上や地域の雇用・振興につなげていく⑮。
⑩ 分かりにくい表現です。また、ここは解決策を書くパートなので、有効性を示すのではなくやることとして書きましょう。最初のセンテンスの構成は、目的→やること(解決策)の順で書くと良いでしょう。→「経済の基盤となるエネルギーを安定的に供給すること、及び地球温暖化の要因であるCO2の排出抑制を同時に図るため、再生可能エネルギー施設の導入を推進する」
ただし、この修正をした場合でも、天候に左右される再生可能エネルギーは、その導入を推進すればするほど、エネルギー供給は不安定になるのではありませんか。
⑪ 「このため」とありますが、なぜ国や地方自治体が主体となり進める必要があるのか分かりません。前述の内容は、国や地方自治体が進めていくべき理由ではなく、再生可能エネルギー施設の導入が有効であることの節目にすぎません。接続詞がおかしいのと、主張が唐突です。
⑫ 最近の傾向は、予算に限りがあることを前提として解答を求めてくるので、安直に補助金支援との解決方策はお勧めできません(お金が潤沢にあれば、大抵のことは解決してしまいます)。
⑬ 具体的に書きましょう。具体性=技術力と認識しましょう。
⑭ ペロブスカイト太陽電池など次世代装置の実証試験がなぜ地産地消につながるのでしょか。関係性が不明です。
⑮ これもエネルギーの地産地消がなぜ生活利便の向上や雇用創出につながるのか分かりません。要因と結果がむずび付きません。
(2)サーキュラーエコノミーの推進
資源投入量と廃棄物処分量を減少させていく循環ビジネスの市場は今後80兆円規模と見込まれており、地域の雇用・振興に大きく寄与すると考えられる⑯。
このため、地域資源を活用したサーキュラーエコノミー型ビジネスを推進していく⑰。 具体的には、地域の商店街や空きビルなどをリノベーションして、オフィス空間を創出する。また、耕作放棄地や荒廃した里山のバイオマス資源をバイオマス発電燃料やプラスチック代替材として活用⑱する。⑲
⑯ ここは解決策なので現状や効果を書くのではなく、⑩のとおり目的とやることを書きましょう。また、経済に偏重しているように感じます。もっと、環境部門なのですから、環境的側面を書くべきではないでしょうか。
⑰ これでは、前述と同じようなことを述べているにすぎません。もう少し踏み込んだ解決策、つまりサーキュラーエコノミー型ビジネスをどのように推進していくのかといったことを焦点化すべきです。
⑱ これらの事例は、未活用資源の活用事例にすぎません。サーキュラーエコノミーとは、資源を効率的に循環させ、持続可能な社会をつくるとともに経済的な成長もめざす「経済システム」を意味します。これらは、循環した経済システムとは言えないと思います。
⑲ 複数とあるので、最低でも3つは解決策を示しましょう。
3.解決策実行後の新たなリスクと対応策
(1)リスク
各種事業に係る環境・経済・社会上の効果は短期的には把握しにくく、事業が継続されないリスク⑳がある。
(2)対応策
環境・経済・社会上の効果を定量評価する。具体的には、事業全体におけるCO2・廃棄物の削減量、生態系サービスの指標などを算出㉑する。また、経済効果、定住者数や人流等はAIやビッグデータを活用して評価㉒する。定量結果は、産官学や住民で構成される評価検討会や勉強会を通じて、定期的に公表㉓していく。
⑳ これは実行前に存在する既知のリスクであり、新たなリスクと言えるか疑義があります。
㉑ 具体的とあるので、どうやって算出するのかも記述すると良いでしょう。
㉒ これは具体的手段があって良いのですが、なぜAIやビッグデータなのでしょうか。
㉓ なぜ公表するのですか。リスクとの関係性を明確にしましょう。
4.技術者倫理、社会の持続性
(1)技術者倫理
公共の安全を最優先とすることが必要な要点である。
再エネ施設やバイオ発電の建設・運転にあたり、工期の短縮やコスト削減よりも、作業員や住民の安全を最優先とする。また、効果の定量評価にあっては、算出根拠を十分に示し、グリーンウォッシュを回避する㉔。
㉔ これがどのような倫理に配慮した行動なのかを明確にしましょう。
(2)社会の持続性
地域の環境保全に努めることが必要な要点である。
再エネ施設の建設等にあたり、環境に配慮した建設資材の活用や、低炭素型重機を用いる。また、施工に係る建設資材を最小として資材の運搬等のCO2を削減するといった、環境保全上の相乗効果を図ることが有効である㉕。 以上
㉕ 何と何の要素が組み合わさって、どのような効果を大きくしているのでしょうか。