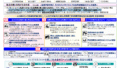口頭試験合否のカギはFAQ
【 技術士 二次試験対策 】
良質な質問をつくろう
技術士口頭試験における「想定質問」の作成は、単なる知識の確認ではありません。作成に当たっては、受験者の思考力・倫理観・実務経験・社会的責任感などを多面的に引き出す問いを構成することが重要です。そこで、オリジナルの想定質問を作成する際に注意すべき点を、体系的かつ具体的に解説します。
想定質問の目的と位置づけ
口頭試験における質問は、以下のような目的を持っています:
- 受験者の理解の深さと論理的思考力の確認
- 実務経験と技術的応用力の検証
- 技術士としての倫理観・社会的責任の自覚
- 制度や政策への理解と提案力の評価
したがって、質問は単なる知識確認ではなく、「考えさせる」「語らせる」構造を持つ必要があります。
想定質問の分類と構造
質問は以下のようなカテゴリに分類できます。この分類を意識することで、質問のバランスと網羅性が高まります。
| 分類 | 内容例 | 目的 |
| 倫理・法令 | 技術士倫理要領、信頼失墜行為、守秘義務など | 社会的責任と倫理観の確認 |
| 制度理解 | 技術士制度の目的、義務と責任、CPD制度など | 制度的理解と自覚の確認 |
| 実務経験 | 経歴説明、課題解決、住民対応など | 実務力・応用力の確認 |
| 社会的課題 | 公益確保、持続可能性、地域課題など | 社会的視点と提案力の確認 |
| 将来展望 | 専門分野の課題、技術士取得後の展望など | 成長意欲と使命感の確認 |
質問作成時の注意点
① 技術士法・倫理要領との整合性
- 技術士法第45条の「信頼失墜行為の禁止」や「守秘義務」など、法令に基づいた質問を設ける。
- 技術士倫理要領の10項目(安全・持続可能性・信頼・有能性・真実性・公正性・守秘・法令遵守・相互尊重・人材育成)を踏まえた設問を意識する。
例:「あなたが関与した業務において、技術士倫理要領の『真実性の確保』が問われる場面はありましたか?」
② 実務経験との接続性
- 「課題」「工夫」「成果」「住民対応」「リーダーシップ」などの観点から掘り下げる。
例:「あなたが担当した業務で、住民との合意形成に苦労した場面は?その際の対応策は?」
③ 社会的視点の導入
- 公益確保、持続可能性、地域課題、災害対応など、社会的意義を問う質問を含める。
- 技術者としての「公共性」「説明責任」「将来世代への配慮」などを意識させる。
例:「あなたの専門分野において、持続可能な社会の実現に貢献できる技術的取り組みは?」
④ 自己認識と展望を問う
- 技術士取得の動機、今後の展望、CPD活動、後進育成など、自己の成長意欲を問う。
- 「技術士としてのあるべき姿」を自ら語らせる設問が有効。
例:「技術士資格取得後、どのような活動を通じて社会に貢献したいと考えていますか?」
質問の設計技法
① オープン・クローズドの使い分け
- オープン質問:自由に語らせる(例:「あなたの考えを述べてください」)
- クローズド質問:知識確認やYes/No(例:「技術士法第45条の内容を説明してください」)
→口頭試験ではオープン質問が中心。思考力・表現力を引き出す。
② 「なぜ」「どうして」を含める
- 単なる事実確認ではなく、理由や背景を語らせることで、論理性と理解度を測る。
例:「なぜ技術士に守秘義務が課されていると考えますか?」
③ 「仮定」「事例」「対立構造」を活用
- 仮定:もし〇〇だったらどうする?
- 事例:〇〇の事例を挙げて説明してください。
- 対立:AとBの利害が対立した場合、どう判断しますか?
→思考の柔軟性と判断力を問う。
質問の質を高める
① 具体性と文脈性
- 抽象的な質問ではなく、業務や社会状況に即した具体的な文脈を与える。
- 「あなたの業務において」「最近の〇〇問題に関連して」などの前置きを加える。
② 多面的な視点
- 技術・倫理・制度・社会・経済など、複数の視点を交差させる。
- 「技術的には可能だが、倫理的に問題がある場合、どう判断するか?」など。
③ 試験官の意図を想定する
- 「この質問で何を見たいのか?」を逆算して設計する。
例:「公益確保に関する質問」→社会的責任感・判断力・説明力を見たい。
作成プロセスのステップ
- 経歴票の内容と照合
- 専門分野の社会的課題の抽出
- 質問分類(倫理・制度・実務・社会・展望)を決定
- 質問文の設計(オープン型、具体性、理由付け)
- 模擬回答を想定し、深掘り可能か検証
- 第三者(指導者・同僚)によるレビュー
良い質問とは何か
良い想定質問とは、以下の条件を満たすものです。
- 受験者の思考を促す問いであること
- 技術士としての資質を多面的に問うこと
- 具体的かつ文脈に即していること
- 倫理・制度・実務・社会のバランスが取れていること
- 模擬回答を通じて自己理解と表現力が高まること