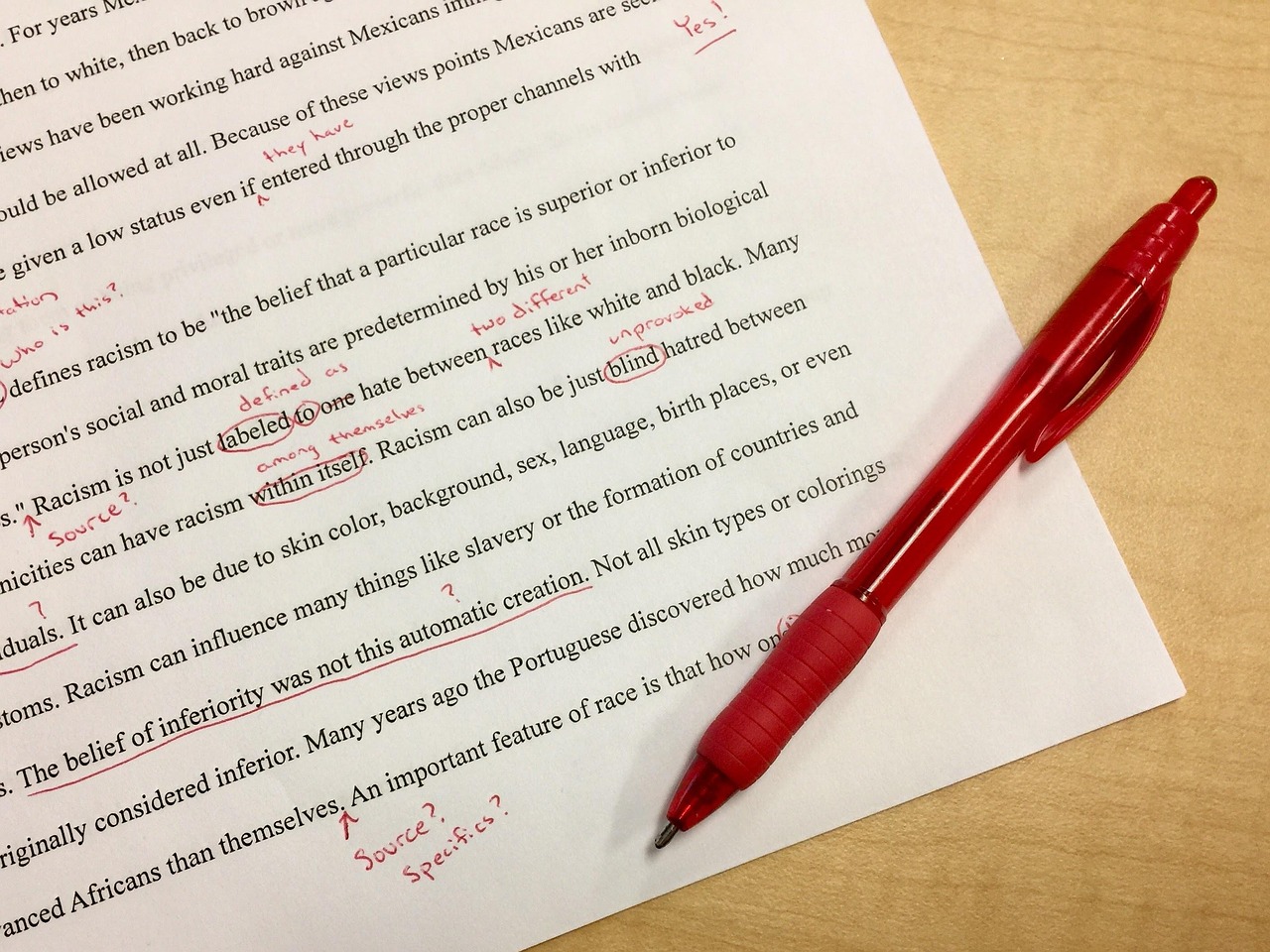添削LIVE
【 技術士 二次試験対策 】
復元論文の活用法
技術士試験を終え、皆様はようやく夏休みですかね!?日々を送る中では、すべて一所懸命というわけにはいきませんから、やるときはやる!、ゆっくりするときはしっかり休養する!といったメリハリが大切です。
ただし、ゆっくりする前にやるべきことが一つだけあります。以前にもご述べましたが(過去記事はコチラ)、復元論文は必ず作成しましょう。記憶は日々曖昧になりますから、忘れないうちに作成することが何より重要です。もう、皆様は作成済みですよね!?
作成した復元論文を作りっぱなしにしては、もったいないです。当然、口頭試験で役立つことは間違いないのですが、もっと有効に活用すべきでしょう。よく事業進めるマネジメント手法にPDCAサイクルがありますが、人生においても有効な手法です。
つまり、反省なくして成長なしです。作った復元論文を客観的に評価し、次につなげることが重要です。まずは、自分自身で論点ズレがないか、もっと技術的な記述ができたのではないか、適切な表現・構成であるかといった視点で添削してみると良いでしょう。
これをやると、もっとこうしとけばよかったと後悔の念に駆られると思いますが、恐れず実践してください。この後悔は、心に強く刻まれますので、以降、同じミスが発生しなくなる確率が格段に上がります。後悔しようがしまいが、結果は変わりません。ならば有効に生かした方がお得です。
セルフチェックを行ったうえで、お近くの技術士に見てもらうと良いでしょう。出来がよくないから、と躊躇してはいけません。辛辣な指摘があっても、その後の技術者人生の血肉になります。身近な人には、さすがにちょっとねぇ・・・という人は、ご投稿をお待ちしております。非公開サービスもありますので、ご検討いただければうれしいです(サービス内容はコチラ)。
復元論文フルセット第1弾 必須科目Ⅰ
早くも登場、令和7年度 建設部門 都市及び地方計画 フルセットを全3回に分けてお届けしたいと思います。本日の第1弾は、みなさん興味津々の必須科目Ⅰー1「持続可能な建設業」になります。多くの人が、こちらの問題を選択したのではないでしょうか。そんな大注目の論文が早くも登場です。みなさん、心してお読みいただければと思います。それでは、早速論文を見ていきましょう(問題文はコチラ)。
(1) 課題の抽出及び内容
①地方建設業の産業維持
地方の建設業はインフラ整備及び防災減災において重要な役割を担っている①。また②地方においては基幹産業として雇用の確保にも貢献している③。しかし、社会環境の変化により、産業の維持が難しくなっている④。ゆえに地方建設業の産業維持が課題である⑤。例えば入札条件の適正化等の管理上の対策が考えられる⑥。
① 記述の内容は問題で示されている内容と同じです。地方に限定しているものの、問題の内容は一般化されたものですから、地方も当然含まれます。不要。
② 接続詞の後ろには読点を打ちましょう。※以下同様。
③ 主語がなく、何が貢献しているのか判然としません(建設業が主語ですかね)。また、建設業が基幹産業となっているのは、地方によるのではありませんか。すべての地方で建設業が基幹産業だと一般化するのは慎重になるべきです。よって、「一部の地方においては」が正しい表現ではないでしょうか。
④ 社会環境の変化とは何を指しているのでしょか。抽象的で、なぜ産業(←これも何の産業なのか不明)の維持が難しくなっているのか分かりません。
⑤ 観点がありません。※以下同様。
建設業は産業の一つですので「地方建設業の産業維持」という表現は重複表現です。書くなら、「地方建設業の維持」となります。さらに、この課題は、地方と限定しているものの「建設業がその役割を果たし続けるうえでの課題」の言い換えにすぎません。これでは、「おいしい料理を作るには?」との問いに「おいしく作ることです」と答えているようなものです。
⑥ ここは課題を書くパラグラフです。不要(解決策のパラグラフで書くべきです)。※以下同様。
②労働環境の改善
建設業は労働時間が全産業平均より高い⑦。労働災害も他産業と比較して多い⑧。また近年は酷暑により熱中症の危険も増大している。ゆえに労働環境の改善が課題⑨である。例えば施工時期の平準化や、ウィークリースタンスによる声掛け等、制度・仕組み上の対策が考えられる。
⑦ 時間のは高い低いではなく、長い短い(あるいは多い少ない)です。また、助詞の使い方がおかしいですね。→「建設業の労働時間は、全産業平均より長い。」
⑧ 前段では、現状しか書かれておらず、なぜ労働環境の改善が必要と考えたのかがはっきりしません。労働災害の防止なのか、担い手の確保なのか、建設業の魅力向上なのか、改善目的が何なのか読み取れません。また、前述の課題もそうですが、社会的な背景に焦点が当たっており、技術的な視点に欠けています。問題で聞いているのは「技術的な課題」です。
③DXによる生産性向上
建設業は一品生産、現地屋外生産、労働集約型産業という構造上の性質がある。そのため製造業のライン生産方式のような自動化は困難であった。しかしAI等のICT技術の進歩により、対応可能性は向上している⑨。ゆえにDXによる生産性向上(i-Construction2.0)のさらなる推進が課題⑩である。
⑨ 何の対応可能性なのか判然としません(自動化ですかね)。また、「AIをはじめとするICT技術の進展」と「自動化」との因果関係が不明瞭であり、なぜ対応可能性が向上するのか分かりません。
⑩ 手段と目的が逆ではありませんか。生鮮性を向上させるためにDXを推進するのではありませんか。また、突如としてi-Construction 2.0の話が出てくるのも違和感があります。i-Construction 2.0 は具体的施策の固有名詞であり、論理展開の土台が整わないまま使用しているので、脈絡のない文章に見えます。
(2) 最も重要と考える課題及び解決策
費用対効果⑪が最も高いため「③DXによる生産性向上」を最も重要と考え、以下に解決策を示す。
⑪ どの課題も、費用も効果も示されていないのに、この課題は費用対効果が高いですといわれても、ただの主観にしか見えません。
①遠隔施工、自動施工の普及
オペレーターが建設機械に乗らずに対応する遠隔施工、自動施工を一般の工事に普及させる⑫。自動施工を行う範囲を現場で視覚的に明示し、効率性を高める⑬とともに不慮の事故を防ぐ⑭。
⑫ 「乗らずに対応」との表現に違和感があります。対応とは何ですか。また、一般の工事も何だか分かりません。
⑬ 視覚的に明示とはどのような行動ですか。抽象的で何を行うのか分かりません。さらに、明示するとなぜ効率性が高まるのかその仕組みも分かりません。すべてが、あいまいで具体性に欠けます。もっと、具体的に書かないと、理屈も分からなければ、技術力も示すことはできません。
⑭ DXによる生産性向上が課題なのに、なぜ事故防止の話をしているのか記述の意図が理解できません。また、解決策は、遠隔施工、自動施工の普及なのですから、自動施工の方法を書くのではなく、普及させるための手立てを書く必要があるのではありませんか。論点が見出しとずれています。
②BIM/CIMの活用
BIM/CIM を納品時の正式な図面として施工まで含めて活用する⑮。例えば3D データに時間情報を加えた4Dモデルで施工ステップをデジタルツインとして表示する⑯。これにより手戻りを防ぎ、施工を効率化する。
⑮ 納品時とは何のどんな時を表しているのでしょうか。また、正式な図面との表現も、正式とは一体何を指していて、どのような行動なのでしょうか。さらに、施工までとありますが、何から何までなのですか。加えて言うなら、施工で終わらせるのもいかがなものでしょうか。国土交通省のガイドラインでは、BIM/CIMデータの納品を「設計成果物」として認定する動きが進んでおり、設計〜施工〜維持管理へのデータ連携が重要課題とされています。視点は良いのですが、説明が十分ではありません。
⑯ 何に時間情報を加えるのか、なぜデジタルツインを活用するのか、といった行動の目的が分かりません。論理的な説明が欠けており、なぜ後述にある手戻り防止がなされるのか理解できません。
③データプラットフォームの構築
現場間のデータ連携の円滑化のため⑰、データプラットフォームを構築する。現場を超えて国土交通省データプラットフォームにも連携できるよう⑱、データを標準化する⑲。
⑰ 現場間とは一体どことどこのことなのでしょか。異なる現場で、なぜ連携が必要なのでしょうか。
⑱ 言いたいことが何か分かりません。現場を超えるとは一体どのような状況なのでしょうか、曖昧です。また、「国土交通省データプラットフォームにも」とありますが、他に何があるのでしょうか。
⑳ 何のデータなのでしょうか。標準化とは一体何をするのでしょうか。とにかく、説明が抽象的で、何をしたいのか、なぜそれをするのか、考えが見えません。
④部材のプレキャスト化
施工の円滑化のため、部材のプレキャスト化等の規格化を行う㉑。価格のみではなく、安全性向上、環境負荷低減効果を評価㉒し(VFM) 大規模部材にも適用する。
㉑ なぜこれがDXなのですか?論点がずれています。
㉒ 行動の目的も、もはや生産性向上でもなくなっています。課題に沿った解決策を書きましょう。
(3) 将来的な懸念事項とそれへの対策
①事故、災害時対応力
デジタル技術が普及すると、現場での作業が減少する㉓。すると詳細な判断の経験が減り、予想外の事故、想定外の災害への対応力が減少する懸念㉔がある。
対策:OJT とOFF-JT を組み合わせ、高技能技術者から若年者への技術継承㉕を行う。またナレッジマネジメントを行う。
㉓ これも理由がないので、なぜ現場での作業が減少するのか分かりません。説明不足です。
㉔ 詳細な判断とは一体何を指しているのでしょうか。抽象的です。また、予想外や想定外なら、経験していないのですから、経験をもってしても対応できないのではありませんか。さらに、対応力は減少ではなく、低下ではありませんか。
㉕ 繰り返しになりますが、予想外や想定外の対応は技術継承できるのか疑義があります。
②1人の裁量の増加
遠隔施工の普及により1人で建設機械を複数台操作する等、1人あたりの責任、裁量が増加する。その状況を適切に評価できない懸念がある㉖。
対策:建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用し、個人の業務を適切に評価㉗する。
㉖ 一つの解決策にフィーチャーした懸念事項が適切な解答と言えるのか疑義があります。前述の懸念事項のように解決策に共通した懸念事項の方が適切であると考えます。
㉗ 現行のCCUSは、技能者が遠隔操作建機や自動施工技術に対応できるかどうかを、資格や履歴から判断することはできるでしょうが、責任の軽重や裁量の大小を判断できるシステムなのでしょうか。この場合は、自動施工等に対応できる技能者の能力評価基準をCCUSに組み込むことが解決策にあたるのではないでしょうか。
(4) 業務遂行において必要な要件
倫理の観点:公共の安全、健康、福利を最優先に行動する。判断にあたっては客観的な情報を基に公正に判断する㉘。
社会の持続性の観点:気候変動への対応や生物多様性の確保への対応のため、CO2 削減や環境配慮に留意する㉙。Well-Being への対応のため、豊かな社会に資するインフラ整備を行う㉚。 以上
㉘ 要件なのか、留意点なのかよく分かりません。「・・・が要件である」、「・・・に留意する」といった具合に明確に解答しましょう。
㉙ 「生物多様性の確保への対応」冗長的な表現です。→「生物多様性の保全」
また、環境配慮は手段として語られていますが、抽象的で行動が見えません。
㉚ これも、要件なのか、留意点なのかよく分かりません。さらに、Well-Beingと持続性との関係もよく分からないですし、豊かな社会に資するインフラ整備も曖昧でどのような行動なのか不明確です。