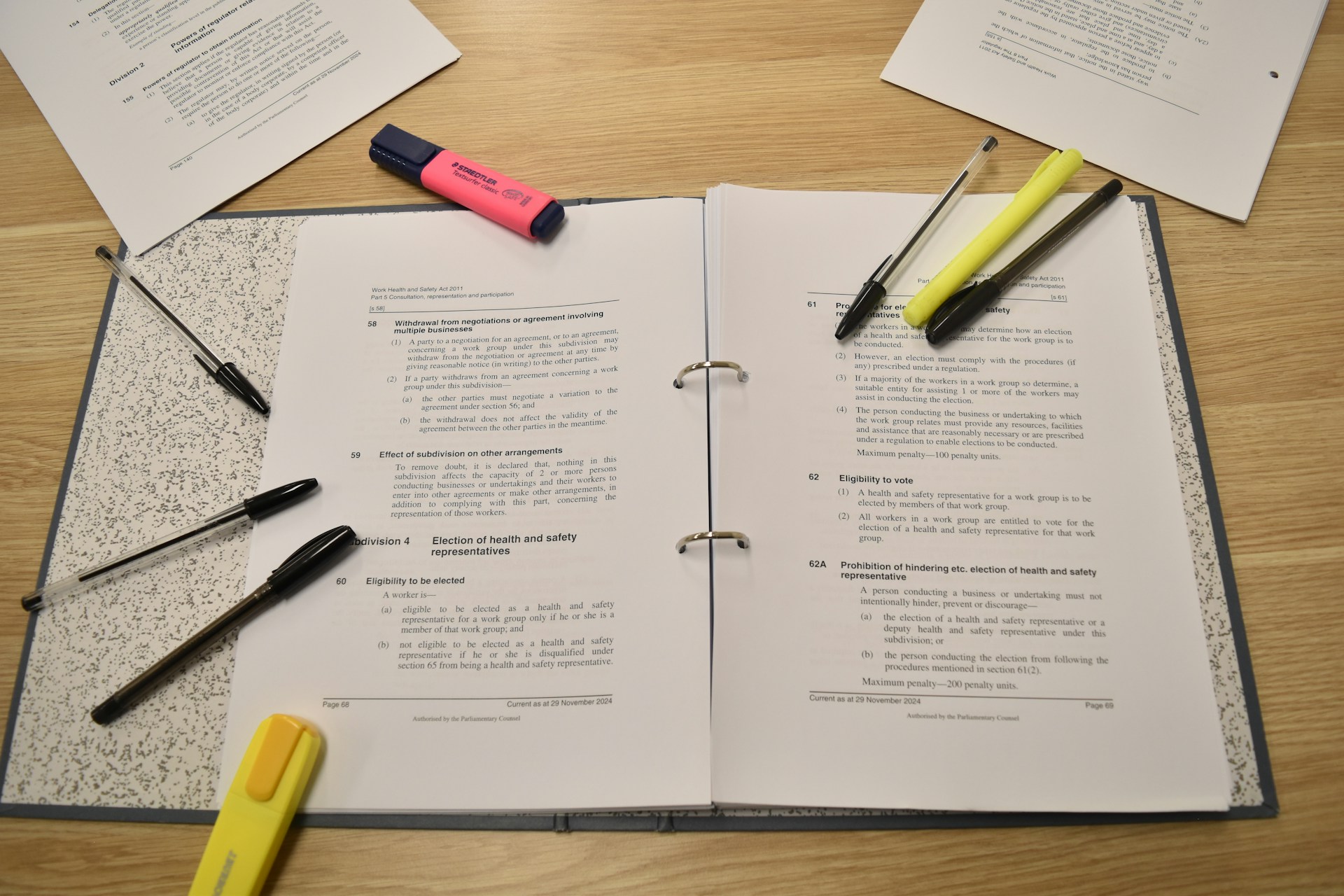添削LIVE
【 技術士 二次試験対策 】
アンテナを高くして時事(社会)問題を把握せよ
今回の試験の全貌が明らかとなっていく中、痛感したことは時事問題がやはり重要だということです。出題の傾向は、注目される社会問題を背景にテーマが設定されています。世の中で、どんなことが問題視されているのか、建設業の抱える問題は何か、それらを解決するためにどのような措置が検討されているのか・・・
これらを常日頃から考え、情報収集することがいかに大事なのかということです。これは、二次試験対策に限ったことではありません。技術士になってからも、習慣化する必要があります。昨今は、土木技術は、凄まじいスピードで進展しています。必死でついていかないと、すぐに置いてきぼりです。
「技術士なのに、こんなことも知らないの?」と思われてしまっては、技術士資格を持っていない状況よりも、なお悪い状況に陥ります。技術士資格は、持っているだけではクソの役にも立ちません。重要なのは、持っているにふさわしい人物であり続けることなのです。
もちろん、技術士になるためには、もう一つの関門である口頭試験を突破しないとなりませんが、この関門においても社会動向を把握することが大切になります。技術士を目指したその日から、最新情報や社会問題をキャッチすることは、もはや生活の一部にする必要があります。
私は、国交省の報道発表を毎日チェックするようにしています。また、白書や予算など一大イベントが発生した時は、腰を据えて読み解くことを心掛けています。私は、みなさんの協力者であり続けたいと考えているため、このような行動をとっていますが、みなさんも自分の状況に応じてアンテナを張る必要があります。
私は仕事上、様々な人々にお会いしてコミュニケーションをとる場面が多いのですが、最新動向を踏まえた会話をすることで、相手の信頼感は高まりますので、結構、交渉や合意形成を円滑化することができます。情報キャッチは、それなりの労力を必要としますが、信頼感を得られること等を考えると意外にタイムパフォーマンスは良いのではないでしょうか。
もう、みなさんは隙間時間の使い方などを習得していると思いますので、これを習慣化して情報取得に充てると良いでしょう。もちろん、これから技術士を目指す人も、情報収集を今から少しづつ積み上げていくと、相当のアドバンテージを得ることができるでしょう。
さあ、みんなアンテナを高く、社会問題を認識し自分のできる解決策に取り組もう!それこそが、合格への最短距離であり、技術士にふさわしい行動と言えます!!
復元論文フルセット第3弾 選択科目Ⅲ
本日の添削LIVEは、復元論文フルセット最終回になります。私は、選択科目Ⅲが最も難しい問題であると考えております。なぜなら、頭のてっぺんから足のつま先まで、技術力を全力で示す必要があるからです。そんな選択科目Ⅲですが、今回ご紹介するのは都市及び地方計画の「立地適正化計画を活用したまちづくり」になります。立地適正化計画は、2014年8月に都市再生特別措置法が改正された際に制度化されましたので、2024で10年を迎えています。こうした周年トピックも出題傾向高めです。それでは、早速論文を見ていきましょう。
Ⅲー1 我が国の都市における今後のまちづくりは、人工の急激な減少と高齢化を背景にしながら、持続可能で安全・安心して暮らせる都市を目指す必要があり、御油性と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設され多くの都市で活用されてきている。
人口減少傾向である人口30万人規模の地方都市において、新たに立地適正化計画を作成して、まちづくりに取り組むこととなった。当業務を担当する「都市及び地方計画分野」の技術者として、以下の問いに答えよ。
(1)上記のような地方都市において、立地適正化計画を活用してまちづくりに取り組むに当たり、多面的な観点から技術課題を3つ抽出し、観点を明記したうえで、それぞれの技術課題の内容を示せ。
(2)前問(1)で抽出した技術課題のうち元も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する内容を示せ。
(3)前問(2)で示した解決策に関連して、立地適正化計画作成後に計画に基づく取組を進めていくなかで、新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
(1) 課題の抽出及び内容
①well-being のまちの実現①
都市には従来、空間や機能が求められてきた②が、一定程度充足してきた。一方、近年はライフスタイルの多様化が進み、多様な価値感③を満たすようなwell-beingなまちの実現が求められている④。
① →「well-beingなまちの実現」
② 空間や機能といった表現は、抽象的過ぎて何が求められてきたのか分かりません。
③ 同じような説明が繰り返されているように見えます。また、「価値観」ですね。
④ 観点もなければ、課題も何だか分かりません。問いに対して明確に解答しましょう。→「・・・の観点から、・・・が課題である」
また、立地適正化計画の活用とどのように関係があるのか分からないうえ、なぜwell-beingなのかも分かりません。さらに、これは立地適正化計画を策定した結果としての効果に見えます。適切な課題設定と言えるか疑問です。脈絡がなく唐突であることに加え、技術的な課題提起であるかも疑義があります。
②防災指針による防災減災対策
近年は災害の激甚化、頻発化が進んでおり⑤、都市においても水災害に対して様々な対策が必要となっている⑥。地震に対しても対策を要している⑦。ゆえに立地適正化計画に防災指針を設け、ハザードエリアの居住者に対して安全な場所への誘導を進めることが課題⑧である。例えば防災集団移転促進事業による移転が考えられる⑨。
⑤ 「進んでいる」との表現に違和感があります。→「近年、災害が激甚化・頻発化しており」
⑥ 災害全般の話をしていたのに、対策はなぜ水災害に限定しているのでしょうか。さらに、様々な対策という記載も抽象的であり、対策が必要であること自体は言わずもがなです。
⑦ 地震も必要なら、前述は水災害ではなく災害でよいのではありませんか。分けている意図が分かりません。また、記述の必要性については⑥と同じ。
⑧ 背景との関係があまりに希薄であり、防災指針を課題と考えた理由が分かりません。これも、脈絡がない文章です。また、居住者に対して安全な場所への誘導としては、避難誘導に見えます。居住者ではなく、居住の誘導なのではありませんか。
⑨ ここは課題を書くパラグラフです。不要(解決策のパラグラフで書くべきです)。
③地域公共交通計画との連携
コロナ危機後、テレワークの普及が進んだこともあり⑩、公共交通利用者の減少、交通事業者の収支悪化、サービス水準の悪化が負のスパイラルを描いている⑪。しかし市民の利便性の維持、気候変動や環境への対応の観点から、公共交通の維持が必要である⑫。ゆえに立地適正化計画と地域公共交通計画が連携したネットワーク形成が課題⑬である。
⑩ 「進んだことも」とありますが、これは追加の意味を持たせた助詞ですよね。何に追加しているのか分かりません。
⑪ 負のスパイラルですから、循環しながら低下する様子を表す必要があります。利用者減少→収支悪化→サービス低下→さらに利用者減少といった循環を説明しないとスパイラルになっていません。さらに描いているという口語調の表現も気になります。
⑫ 細かい話ですが、市民は限定的です(区民や町民もいます)。また、生活利便性の維持は分かりますが、気候変動や環境への対応は関係性が不明確です(CO2削減ですかね?)。
⑬ これも脈絡がありません。なぜ両計画を連携させる必要があるのか、なぜネットワーク形成が必要なのか。さらに、ネットワークとは一体何のネットワークなのでしょうか。公共交通の維持が必要であれば、地域公共交通計画の策定で済むのではありませんか。もっと、連携の必要性を背景で説明すべきです。
(2) 最も重要と考える課題及び解決策
「well-being の⑭まちの実現」は日常生活に直結するため⑮、最も重要と考え、以下に解決策を示す。
⑭ →「な」
⑮ そもそも課題が漠然としているので、日常生活に直結しているのか判断できません。さらに、公共交通の維持も生活に直結しているのではありませんか。最も重要と言えるのか疑義があり、選択の理由になっていないと思います。
①特定用途誘導地区の活用
中心市街地に特定用途誘導地区を設定⑯し、医療(病院)等の特定用途に限定して容積率等を緩和する⑰。これにより老朽化した既存病院のような基幹施設を再整備⑱する。
⑯ なぜ中心市街地なのですか。
⑰ なぜ医療なのですか。さらに、これらの行動がなぜ多様な価値観を満たすwell-beingなまちになるでしょうか。全く理解できません。
⑱ 基幹施設とは何ですか。老朽化の再整備でなぜ良績率を緩和する必要があるのですか。説明不足で、行動の動機も成果も不明です。
②誘導施設整備区を活用した土地区画整理事業
空き地が点在する、土地のスポンジ化が進行した地区⑲に対しては、誘導施設整備区を活用した土地区画整理事業を実施する⑳。これにより空き地による懸念(防犯性の悪化、悪臭、火災等)を解消し、賑わい施設を整備する。
⑲ 同じような説明が繰り返されているように見えます。スポンジ化の説明は不要でしょう。→「土地のスポンジ化が顕著な地区」
⑳ この制度はスポンジ化対策には有効ですが、なぜ多様な価値観を満たすwell-beingなまちになるでしょうか。スポンジ化対策をするとwell-beingなまちになるというロジックが分かりません。また、誘導施設整備区は、土地区画整理事業の事業計画内で定めることが可能であり、根拠法令も都市再生法です。立地適正化計画との関係性が希薄であり、題意にも課題にもマッチしている内容とは思えません。
③コモンズ協定の活用
商店街や自治会に対してコモンズ協定の活用を提案する㉑。これにより商店街の通り抜け通路のような都市の余白となっている空間を維持㉒する。承継効により所有者が変更となっても効果が維持されるため、空間が安定的に維持される効果㉓がある。
㉑ 繰り返しになりますが、well-beingなまちとどう関係しているのか分かりません。
㉒ 「効果が維持されるため、・・・維持される効果がる」という構文に違和感があり、前後で同じようなことを繰り返し述べているように感じます。
④駐車場の出入口制限
路外駐車場の出入口制限を行う。これにより市街地の安全性、回遊性を向上する㉓。
㉓ さすがに内容が浅薄すぎます。なぜ安全性や回遊性を向上させるのですか。また、どうして回遊性が向上するのですか。さらに、well-beingなまちとの関係も分からなければ、立地適正化計画の関連性も不明です。説明不足です。加えて、駐車場配置適正化区域などの制度活用なども記載しないと、専門的かつ技術的な記述になっていません。
(3) 将来的な懸念事項とそれへの対策
①空き家の増加
立地適正化計画によって誘導を行っても、人口が社会全体として減少しているため、空き家が増加していく懸念㉔がある。
㉔ これを書いてしまっては、立地適正化計画を否定しているように見えます。また、減少する人口規模と都市の規模がミスマッチだから生じる懸念事項だと考えます。したがって、取り組みを進めていく中で生じる懸念というより、計画が甘かったことによって生じる問題であると考えます。問題の条件を満たしておらず、かつ国の政策を否定する内容に見えるため、不適切な解答に見えてしまいます。
対策ⅰ)空き家は相続時に発生する場合が多いため、相続の行政手続きの際に、空き家バンクへの登録や情報提供等の働きかけを強化する。
ⅱ)空き家対策法に基づく空家等活用促進区域、空家等活用促進指針を設定し、用途変更を円滑化する。併せてリノベーションにより新たな用途を導入する。
ⅲ)管理不全空家、特定空家に対する行政の対応を強化する。
②所有者不明土地の増加
高齢化により相続が多く発生し、所有者不明土地が増加する懸念がある㉕。
㉕ これも、立地適正化計画を策定した後の取組みを行っていく中で発生する問題とは思えません。立地適正化計画と関係のない問題ですし、高齢化するのは新たに浮かび上がってくる問題でもありません。問題の条件を満たした解答と言えないと思います。
対策ⅰ)地域利便増進事業として利用権を設定する。
ⅱ)固定資産税課税台帳等の情報を活用して所有者を確定する。
ⅲ)グリーンインフラを活用して地域で活用する。
③居住誘導区域外への対応
居住誘導区域外の居住者の生活水準確保の懸念がある。
対策)誘導区域内への移転を促進するとともに、ドローン物流、遠隔医療で生活水準を確保する。以上