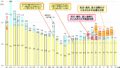添削LIVE
【 技術士 二次試験対策 】
維持管理を極めよう
前回の投稿(コチラ)で予算要求について紹介しましたが、中でも注目されるのが「埼玉県八潮市の道路陥没事故等を踏まえたインフラ老朽化対策等による予防保全型のインフラメンテナンスの実現」です。予算項目にもかかわらず「埼玉県八潮市の道路陥没事故」と事例が示されていることに、その関心の高さがうかがえます。
これからの社会動向は計り知れませんが、現時点ではインフラメンテナンスが最も警戒すべきテーマでしょう。このインフラメンテナンス周辺の知識は、深めておいて損はないと思います。必須科目で出題されずとも、選択科目で関係する問いは出てくる可能性は高いでしょう。
メンテナンスで押さえておきたいのは、やはりICT技術です。ドローン、AIによる画像解析、センシング技術、BIM/CIMによる情報統合、ロボティクス技術などなど、これらを聞いてピンとこない人は、しっかりと習得しておきましょう。
さらに、インフラメンテナンスは第2フェーズに突入しており、その取り組みとして押さえておきたいのが「地域インフラ群再生戦略マネジメント」です。これを知らずして、インフラメンテナンスは語れません。バッチリ理解しておくことを強くお勧めします。
特に、インフラメンテナンス2.0と従来のインフラメンテナンスの違いも押さえておきましょう。新たな取り組みをフィーチャーできれば、高得点が期待できます。また、制度設計の背景にある社会課題も把握すれば、必須科目の課題提起もしやすいです。
インフラメンテナンスが熱い!
「労働力不足×維持管理」前編
ということで、本日の添削LIVEは、建設部門 必須科目Ⅰ「労働力不足×維持管理」をお届けします(問題はコチラ)。これは令和7年度の予想問題として本サイトで公開し、論文を投稿いただいたものです。令和8年度においても、維持管理は大注目のトピックになりますので、参考になると思います。また、口頭試験においても、話題になる可能性がありますね。みんな大注目の論文を早速見ていきましょう。全4回の投稿のうち、今回は第1弾として、前半戦をお届けします。
初稿
1.多面的な課題とその観点
(1)デジタル技術者の確保
2013年の社会資本メンテナンス元年からの約10年間、社会インフラに対する様々な取り組みを行ってきた①。しかし、対象施設の多さや近年の激甚化・頻発化する自然災害対策等、限られた人材でインフラ施設を維持管理するには従来の対応のみでは限界がある②。少ない労働力で適切に対応するにはデジタル技術③を活用した取組みが必要不可欠である。よって、人材面の観点から、デジタル技術者の確保が課題④である。
① 「様々な取り組みを行ってきた」では何も説明していないのと同じです。
② 「しかし」とは何に対する逆接なのか、対象施設とは何か、なぜ限られているのか、将来の対応とは何か、何一つ分かりません。すべてが抽象的で、独りよがりです。読み手が理解できる説明とすることをまずしっかりと意識しましょう。
③ なぜデジタル技術なのかといったことも何も説明がなく、脈絡がありません。
④ 人手不足を解消したいのか、デジタル技術を導入したいのか論点がぼやけています。
(2)予防保全への本格転換の加速化
社会資本施設が適切に維持管理されておらず、老朽化による水道管の破裂や道路陥没等の事故が発生している。これにより、断水や通行規制など都市基盤に影響が生じている⑤。このような状況の中、従前の事後保全から省力化やコスト縮減に効果のある予防保全への転換が急務⑥である。よって、仕組み面の観点から、予防保全への本格転換の加速化が課題⑦である。
⑤ 水土管の破裂、道路陥没といっているので、その影響があることは書かずとも伝わるのではありませんか。
⑥ これも唐突です。事故の話から、急に予防保全と言われても、飛躍した主張です。なぜ予防保全なのか、事故との関係何なのか、なぜ省力化やコスト縮減の話をしているのか、このような説明がないまま予防保全が急務だと言われても理解できません。
⑦ 予防保全は現状どのような状況なのか説明されておらず、本格転換が何なのか分かりません。また、予防保全の転換が必要、だから予防保全が課題との説明は、同じことを何度も説明しているように見えます。背景は、予防保全ではない異なる表現が望まれます。
(3)インフラ分野のDX化
現在、約300万人いる建設技術者は今後10年で約100万人が高齢化により離職するとされている。さらに、2024年からの時間外労働の上限規制により労働力の低下が懸念される。このような状況の中、短時間勤務、リモートワーク等の柔軟な働き方を実現する上でも、魅力的な職場環境づくりと生産性の向上⑧は急務となっている。他方、デジタル技術は急速に発展しており、生産性を補う⑨技術として期待されている。よって、生産性の観点からインフラ分野のDX化が課題⑩である。
⑧ これも柔軟な職場環境を実現したいのか、生産性の向上を図りたいのかよく分かりません。論点を明確にしましょう。
⑨ 生産性を補うとはどのような行動なのですか。
⑩ 観点は異なるものの、デジタル技術者の確保が課題と主旨は同じではありませんか。多面的という条件を満たしているのか疑義があります。
2.最も重要な課題と解決策
時間外労働の上限規制はすでに始まっており、早急な対応が必要⑪なため「インフラ分野のDX化」を最も重要な課題に選定し、解決策を以下に示す。
⑪ ⑩のとおり、デジタル技術者の確保も当てはまりませんか。理由がダメというより、同じような課題設定をしていることが問題です。見直しましょう。
(1)ICT技術の活用
安全性の向上及び省力化、少人化を図るため⑫、ドローンやロボット等のICT(情報通信技術)建機⑬を全面的に活用する⑭。具体的には、測量の場合、短時間の作業で詳細な三次元地形情報を得ることが可能となる⑮。また、高所での橋梁の点検・診断においては、従来は交通規制を行い、橋梁点検車を用いて点検を実施していた⑯。遠隔操作が可能なドローンを利用することで、作業が困難な高所の点検を安全に効率よく行うことができ、省人化、省力化が可能となる⑰。
⑫ 課題では、生産性の観点からとあるので、その目的は生産性の向上なのではありませんか。省力化や省人化は関連した目的ですが、安全性は突如としてできてきましたね。解決策で記述すべき目的は、課題での背景を踏まえたものにすべきです。
⑬ 建機とは建設機械のことですよ。ドローンやロボットは建機ではないと思います。
⑭ 何に活用するのですか。
⑮ 可能性ではなく、解決策を書きましょう。また、何を用いているのですか。説明が断片的で全容が分かりません。
⑯ ここは解決策を書く場所です。昔の状況ではなく、何をどのようにして省力化を図るのかといった事柄を書くべきです。この場合であれば、ドローンを用いて、交通規制を行うことなく、高所の点検を実施するといった表現が考えられます。
⑰ これも可能性ではなく、やること(解決策)として書きましょう。また、省力化、省人化といった効果は最初に書いてあるので重複しています。不要。
(2)BIM/CIMの活用
関係者間での作業を効率的に行うため、調査・設計から維持管理までの全行程でBIM/CIMの⑱3次元データを共有する。また、技術的な情報だけでなく、コストや価格情報⑲をBIM/CIMデータに付与する。これによりコスト管理、労務管理⑳の一層の効率化が可能となる。また建設事業に関する様々な情報がBIM/CIMに関連付けされるシステムを整備する㉑。
⑱ →「BIM/CIMを用いて」
⑲ 同じではありませんか。
⑳ 労務管理が効率化される仕組みが分かりません。
㉑ これも抽象的です。建設事業に関する様々な情報とは何ですか。BIM/CIMに関連付けされるシステムとは何ですか。
(3)国土交通データプラットフォームの活用
国・自治体等関係者間での情報共有と劣化予測を可能にする国土交通データプラットフォームを活用し、新たなサービスの創出や官民協働の推進を行う㉒。これにより、更なる生産性の向上を図る㉓。具体的には、インフラの点検情報を共有し、専門家による遠隔診断を実現㉔する。発注者、点検者、専門家等の関係者間で横断的に対策検討を行う㉕。人手不足が顕著な地方自治体においても効率的な検討、維持管理が可能となる㉖。また、交通、防災等様々な分野の情報を一般公開し国民のインフラへの関心、持続可能な社会の構築を目指す㉗。
㉒ 国土交通データプラットフォームで劣化予測が行えるのですか。また、国・自治体等関係者間での情報共有という機能を説明しているのですか。国と自治体間で情報共有する目的も分からなければ、後述には官民協働の推進を図るとあります。一体、誰が何をするのでしょうか。
㉓ なぜ生産性の向上が図れるのですか。
㉔ 国・自治体等関係者間での情報共有と劣化予測はどうなっているのですか。専門家とは誰なのでしょうか、民間との協働の例示ですか。
㉕ プラットフォームとどのように関係しているのですか。
㉖ なぜですか。
㉗ 目標ではなく、やることを書きましょう。ここでの解決策は、新たなサービスの創出や官民協働の推進ではないのですか。全体として、理由や仕組みの話もなく、説得力に欠けます。また、論点もあっちこっちに拡散し、とりとめのない説明になっています。
3.新たに生じうるリスクと対応策
上記の解決策では、衛星やドローンによる点群や映像取得・解析㉘でデジタルデータ利用が増加する。そのため、ハッキングやマルウェアなどのサイバー攻撃のリスクが高くなる。多くのデータに問題が生じた場合、解決に時間と労力が必要となり、生産性が低下する㉙。VPN接続やファイアウォール、電磁シールドなどの多重防御を実施する。また、BCP(事業継続計画)にシステム障害項目を加え、サイバー攻撃への対応を行う。
㉘ このような話は解決策のどこに書いてあるのですか。
㉙ リスクの影響まで書かなくても理解できると思います。
チェックバック①
1.多面的な課題とその観点
(1)労働力の確保
建設業は労働力に依存している。しかし、生産年齢人口の減少や3K(きつい、汚い、危険)、週休2日制の未実施といった劣悪な労働環境が影響し、人手不足が深刻化している。さらに、担い手となる若者から敬遠されやすく①、建設業の存続も危惧される。よって、持続性の観点から労働力の確保が課題②である。
① この内容は、前述の内容と重複しているように見えます。前述の内容を含め整理が必要です。→「しかし、生産年齢人口の減少に伴い、従来の労働環境の厳しさが人手不足を加速させている。特に、長時間労働や週休2日制の未整備、3K(きつい・汚い・危険)といった要因が若年層の参入を妨げており、建設業の存続も危惧される。」
② 労働力が不足しているから、労働力確保が課題では当たり前ですよね。課題は、もう一歩踏み込んだ提起が必要です。この文脈ですと、労働環境の改善といった課題が想起されます。
(2)予防保全への本格転換の加速化
高度成長期以降に集中的に整備された社会資本施設が財源不足により適切に維持管理されていない。最近では、耐用年数を超えた水道管が老朽化により破裂し、道路陥没等の事故が発生している。そのため、老朽化が表面化、問題化する前段階での対応が必要である③。よって、仕組み面の観点から、予防保全への本格転換の加速化が課題④である。
③ 事故が起きる前に対応が必要なのは当たり前ですし、やりたくても前述にあるように財源が不足していてできないのではありませんか。コストを縮減して進めるといった視点が必要性ではありませんか。
④ 予防保全は現状どのような状況なのか説明されておらず、本格転換が何なのか分かりません。もっと、急ぎ転換する状況を説明しましょう。これを踏まえて背景を再構築すると次のようになります。
→「高度成長期に整備された社会資本施設は、財源不足により適切な維持管理が行われず、老朽化が進行している(←加速化の必要性)。これにより、水道管の破裂や道路陥没などの事故が発生し、事後対応では復旧コストの増大や社会的影響の拡大を招く恐れがある。そのため、損傷が顕在化する前段階で計画的な維持管理(←本格転換の必要性)を早急に実施する必要がある。」
(3)インフラ分野のDX化
現在、約300万人いる建設技術者は今後10年で約100万人が高齢化により離職するとされている。さらに、2024年からの時間外労働の上限規制により労働力の低下が懸念される。このような状況の中、デジタル技術は急速に発展しており、労働力不足を補う技術として期待されている⑤。よって、生産性の観点からインフラ分野のDX化が課題である。
⑤ 人手不足は最初の課題で述べていますので、少し視点を変えDXの目的を明確にしましょう。→「業務の効率化や省人化を支える手段として期待されている」
2.最も重要な課題と解決策
デジタル技術の活用は即効性があり、早急な対応が可能なため「インフラ分野のDX化」を最も重要な課題に選定し、解決策を以下に示す。
(1)ICT技術の活用
生産性の向上及び省力化、少人化を図るため、ドローンや衛星等のICT(情報通信技術)を全面的に導入する。具体的には、ドローン測量の場合⑥、短時間の作業で詳細な三次元地形情報を得ることができる⑦。また、ドローンを用いて、交通規制を行うことなく、高所の点検を実施する。遠隔操作が可能なドローンを利用することで、作業が困難な高所の点検を少人数で安全に効率良く行うことができる⑧。
⑥ すべてドローンの話なので、ドローンのケースを説明することを伝えた方がよいでしょう。またこの場合ドローンの例示なので、「例えば」の方がよいですね(その他のICTの説明がないため)。
⑦ 解決策なのでやることとして書きましょう。
⑧ また高所作業の話になっています。高所に限らず、安全性に関する効果を説明すれば良いのではないでしょうか。前述も含め修正すると「例えば、測量にドローンを活用し、短時間で高精度な三次元地形情報を取得する。また、遠隔操作により、作業員が危険な場所に立ち入ることなく、安全かつ少ない人数で点検を行う。さらに、道路上の点検では、ドローンを活用することで交通規制を行わずに作業を実施する。」
(2)BIM/CIMの活用
関係者間での作業を効率的に行うため、調査・設計から維持管理までの全行程でBIM/CIMを用いて3次元データを共有する。例えば、地下埋設物の場合、設計段階の3Dデータに調査結果を反映させることで、構造物の位置確認や構造概要の把握が可能となる。これにより、工事の手戻りが減り効率的な維持管理を実施する。また、視覚的な情報伝達が可能となるため、地元説明会等において同意形成が容易となる。その他、技術的な情報だけでなく、価格情報をBIM/CIMデータに付与する。これによりコスト管理の一層の効率化が可能となる⑨。
⑨ これも可能性になっています。解決策なのでやることとして書きましょう。→「地下埋設物については、設計段階の3Dデータに調査結果を反映し、構造物の位置や概要を正確に把握する。これにより、工事の手戻りを削減し、維持管理を計画的かつ効率的に実施する。また、視覚的な情報を活用して地元説明会を行い、合意形成を円滑に進める。さらに、技術的な情報に加えて価格情報をBIM/CIMデータに統合し、コスト管理の精度を向上させる。」
(3)国土交通データプラットフォームの活用
国・自治体・建設業者等関係者間で道路、河川、都市などの各分野のインフラ施設の情報共有を可能にする国土交通データプラットフォームを活用し、持続可能な社会の構築や適切な維持管理を行う⑩。具体的には、インフラの点検情報を共有し、コンクリート診断士による損傷状況確認や劣化予測の遠隔診断を実現する⑪。発注者、点検者、専門家の関係者間で横断的に対策検討を行い、一元化したデータ管理を行う⑫。人手不足が顕著な地方自治体においては類似の損傷に対する検討データを利用することで、効率的な維持管理が可能となる⑬。また、インフラ情報を一般公開することでデータ収集や確認の手間が省け、業務効率化となる⑭。
⑩ これは題意そのものであり、問いと回答が同じになっています。不要。→「国・自治体・建設業者などの関係者間で、道路・河川・都市などのインフラ施設の情報を統合管理し、効率的かつ効果的な維持管理を実現するため、国土交通データプラットフォームを活用する」
⑪ アウトカムが診断というの物足りない感じがするのと、遠隔診断なのかも疑義があります。→「コンクリート診断士による損傷状況の評価を実施するとともに、劣化予測モデルを活用した補修計画を策定する」
⑫ 対策検討を行った結果として、データ管理では釈然としません。目的は意思決定なのではありませんか。→「意思決定の迅速化を図る」
⑬ 可能性ではなく、やることとして書きましょう。→「地方自治体では、過去の類似損傷データを参照することで、点検・補修の判断基準を標準化し、限られた人的資源の中でも効率的な維持管理を行う」
⑭ 一般公開の効果は、手間云々ではなく、その結果による幅広い視点で説明すべきです。→「民間事業者が新技術の開発やコスト削減を進め、業務効率化を加速させる」
3.新たに生じうるリスクと対応策
上記の解決策では、衛星やドローンによる点群や映像取得・解析や各分野のデジタルデータ利用が増加する。そのため、ハッキングやマルウェアなどのサイバー攻撃のリスクが高くなる。対策としてはVPN接続やファイアウォール、電磁シールドなどの多重防御を実施する。また、BCP(事業継続計画)にシステム障害項目を加え、サイバー攻撃への対応を行う⑮。
⑮ 対応が何に対するどのような行動なのかを明確にした方が良いと思います。また、「サイバー攻撃への対応を行う」は当たり前ですので、解答になっていないと思います。→「多層防御を導入し、システムの安全性を確保する。・・・加え、サイバー攻撃による影響を最小限に抑え、迅速な復旧対応を実現する。」
4.業務遂行上必要となる要点・留意点
業務にあたっては、常に社会全体における公益を確保する観点と、安全・安心な社会資本ストックを構築して維持し続ける観点を持つ必要がある。業務の各段階で常にこれらを意識するよう留意する。 -以上-