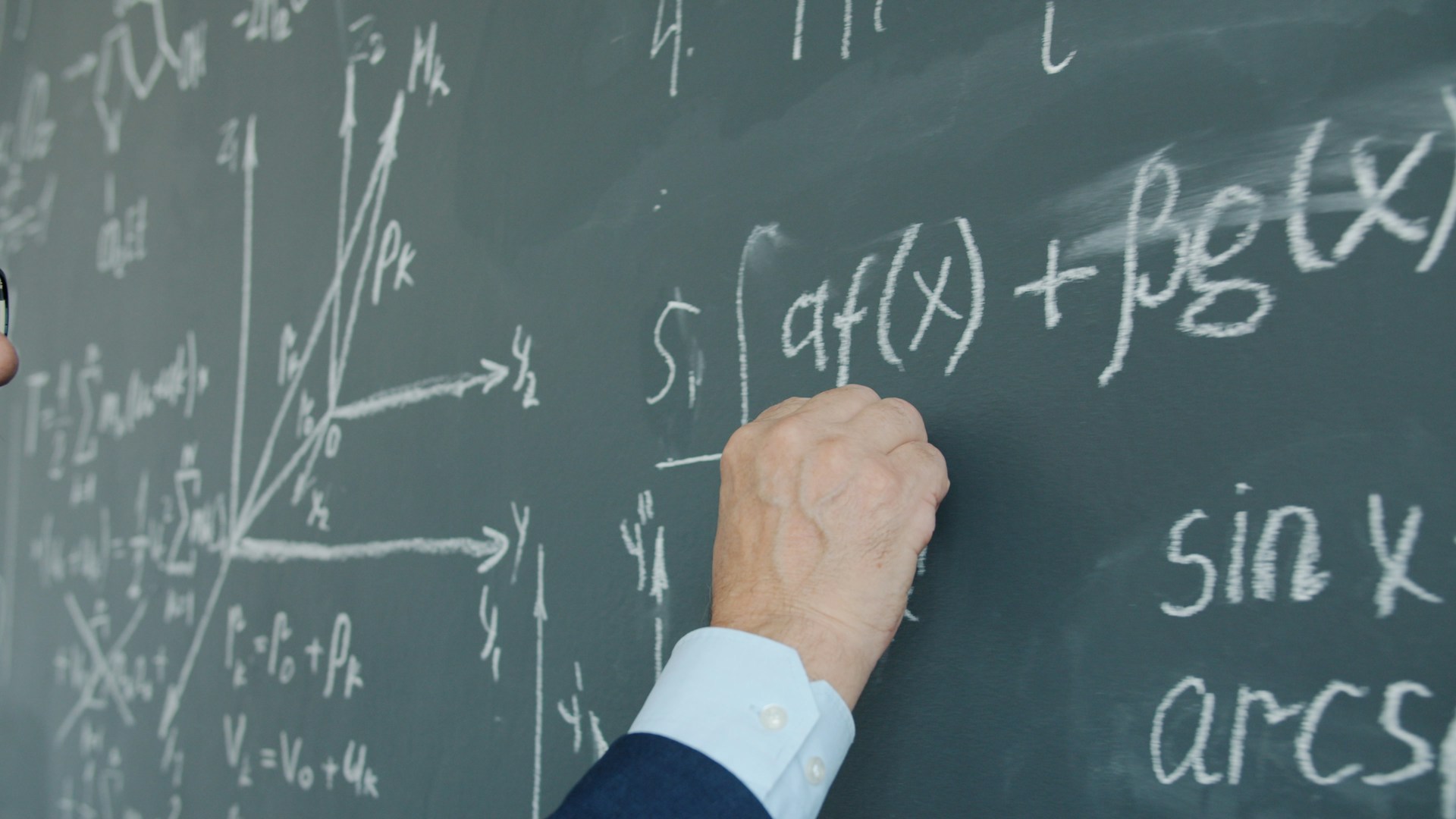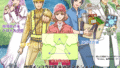法・倫理・資質の“合格方程式”
【 技術士 二次試験対策 】
三種の神器の重要性
技術士口頭試験において「技術士法」「技術士倫理綱領」「技術士のコンピテンシー」は、まさに合格への三種の神器と呼ぶにふさわしい重要要素です。以下では、それぞれの概要と、口頭試験対策としての具体的な活用方法を体系的に解説します。
技術士第二次試験の最終関門である口頭試験は、「筆記試験合格者が技術士としての資質を備えているか」を確認する場です。評価項目は以下の2軸に分かれます。
- 実務能力:コミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメント
- 適格性:技術者倫理、継続研鑽
この評価基準は、技術士に求められる「コンピテンシー(資質能力)」に基づいており、技術士法と倫理綱領は「適格性」の根拠となる法的・倫理的基盤です。
技術士法の活用方法
技術士法は、技術士の資格制度を定める法律であり、以下の義務・責務が明記されています。
- 3義務
・信用失墜行為の禁止
・守秘義務
・名称表示義務 - 2責務
・公益確保の責務
・資質向上の責務
試験対策としての活用法
暗記ではなく「実践経験との接続」
単なる条文の暗記ではなく、自身の業務経験と照らし合わせて、どのように法的義務を果たしてきたかを語れるようにする。
事例準備
守秘義務や公益確保に関する実務上の判断事例を準備し、倫理的ジレンマにどう対応したかを説明できるようにする。
想定問答の準備
「信用失墜行為とは何か」「公益確保のためにどんな行動を取ったか」など、想定問答を作成し、論理的に答える練習をする。
技術士倫理綱領の活用方法
2023年に改定された技術士倫理綱領は、以下の10項目から成り立ちます。
- 安全・健康・福利の優先
- 持続可能な社会の実現
- 信用の保持
- 有能性の重視
- 真実性の確保
- 公正かつ誠実な履行
- 秘密情報の保護
- 法令等の遵守
- 相互の尊重
- 継続研鑽と人材育成
改定では「志向倫理」が強調され、単なる予防ではなく「技術者として何を目指すか」が問われるようになりました。
試験対策としての活用法
自己の行動との照合
各項目について、自身の業務経験と照らし合わせて「どのように実践したか」「課題があったか」を整理する。
倫理的判断の事例化
例えば「持続可能性」や「秘密情報の保護」に関して、具体的な判断事例を準備し、倫理的な配慮を説明できるようにする。
志向倫理の視点で語る
「技術者として何を目指すか」「社会にどう貢献したいか」といった未来志向の語り口を意識する。
技術士コンピテンシーの活用方法
技術士に求められるコンピテンシーは、筆記試験で2つ(専門的学識、問題解決)が評価され、口頭試験では以下の6つが問われます。
試験対策としての活用法
自己分析とエピソード整理
各コンピテンシーに対応する業務経験を整理し、「どのような行動を取ったか」「成果は何か」を明確にする。
模擬面接での反復練習
各コンピテンシーに関する質問を想定し、模擬面接で繰り返し練習することで、自然な語り口と論理性を磨く。
継続研鑽の具体策提示
自己研鑽の方法(学会参加、資格取得、社内教育など)や、後進育成の取り組み(OJT、勉強会主催など)を具体的に語る。
三種の神器の統合的活用
口頭試験では、これら三要素を「別々に語る」のではなく、「統合的に語る」ことが重要です。
統合のポイント
倫理綱領と技術士法を背景に、コンピテンシーを語る
例えば「守秘義務を遵守しつつ、関係者と効果的にコミュニケーションを取った」など、法・倫理・資質を一体化して説明する。
事例に三要素を織り込む
実務経験のエピソードに、技術士法の遵守、倫理的判断、コンピテンシーの発揮を織り込むことで、説得力が増す。
「技術士としてのあるべき姿」を語る
志向倫理の視点から、「技術士として社会にどう貢献したいか」「どんな価値を提供できるか」を語ることで、適格性を強く印象づける。
合格への戦略的アプローチ
技術士口頭試験における三種の神器は、単なる知識ではなく「語る力」「つなぐ力」が問われます。以下のステップで対策を進めましょう。
- 技術士法・倫理綱領の理解と事例化
- コンピテンシーごとの自己分析とエピソード整理
- 統合的な語り口の構築(実務経験+志向倫理)
- 模擬面接による反復練習とフィードバック
- 「技術士としての志」を明確にする
このような戦略的アプローチにより、単なる暗記ではなく「技術士としての本質的な資質」を伝えることができ、合格への道が開けます。模擬面接は特に重要です。技術士の先輩がいたら、その方にお願いしましょう。いない人は、家族や友人にFAQを渡して、感想を言ってもらいましょう。FAQは添削サービス(詳細はコチラ)もありますので、良かったら活用してください。