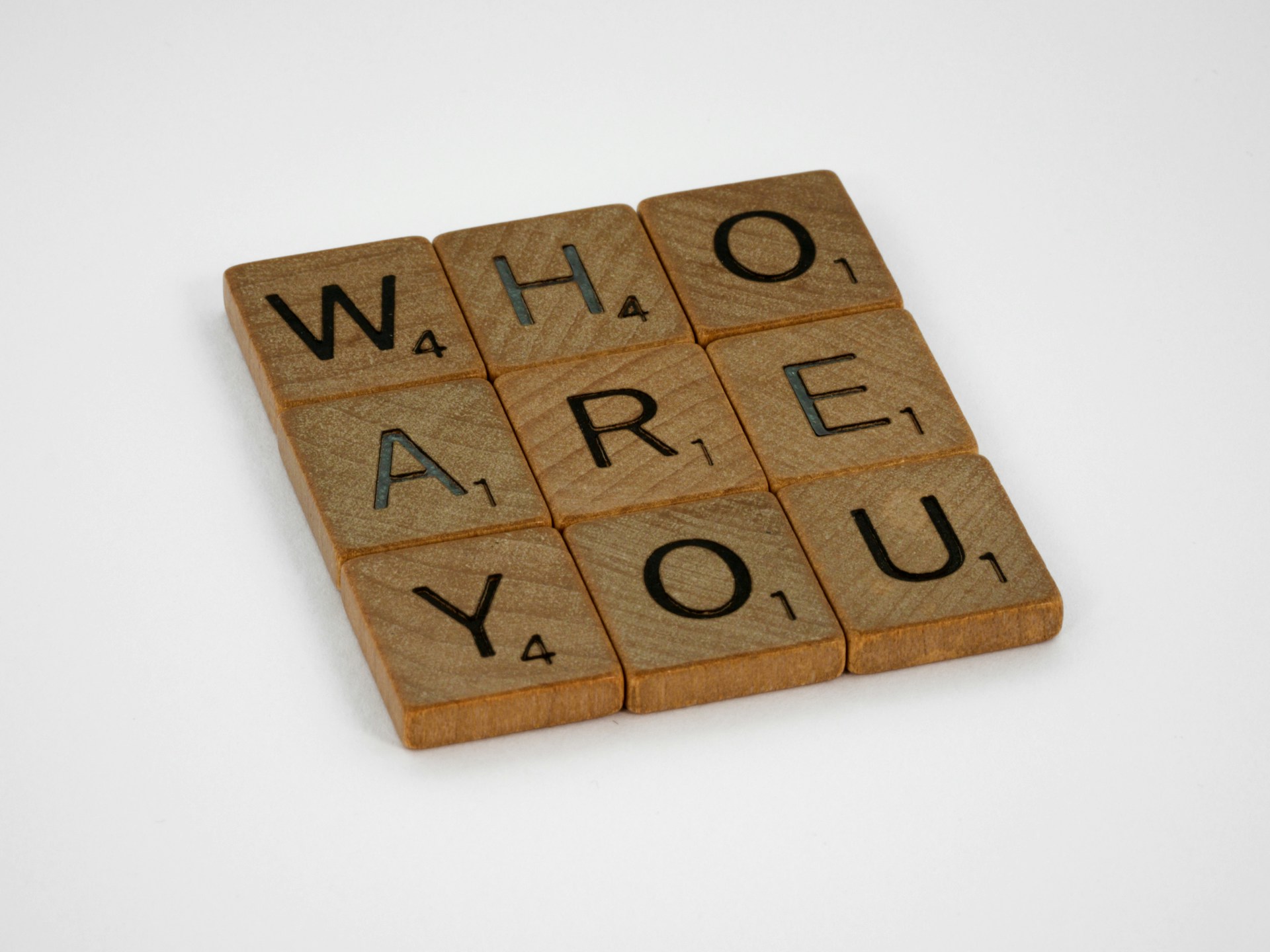口頭試験の質問作成要領
【 技術士 二次試験対策 】
筆記試験の予想問題=口頭試験の想定質問
筆記試験が「設計図」なら、口頭試験は「現場検査」。口頭試験は、「図面通りに動けるか」を見られます。どちらも本番で“技術士にふさわしい自分”を見せるための準備です。筆記だけ鍛えて口頭をサボっては、スーツは完璧なのに寝ぐせ全開で面接に行くようなものです。
口頭試験では、技術士としての考え方・倫理観・説明力が丸裸になります。「あなたの業務が社会に与える影響は?」なんて聞かれて、「えっと…」じゃもったいないです。だからこそ、筆記の予想問題と同じ熱量で、口頭の“想定質問”も作り込むべきです。
準備しておけば、試験官の「なるほど!」を引き出すチャンスが倍増しますよ。技術士法の義務や責務、倫理綱領、コンピテンシー──これらを踏まえた質問を自分に投げてみることで、思考の筋肉が鍛えられ、言葉の瞬発力がつきます。
「業務上知り得た情報をどう管理していますか?」「若手技術者の育成で意識していることは?」など、制度と実務をつなぐ“生きた問い”を準備しておけば、試験官の「この人、技術士だな」と納得する瞬間を引き寄せられます。つまり、想定質問は“口頭試験の予習”じゃなく、“技術士としての自己点検”。
よって、技術士試験の口頭対策で、的外れな質問を作っても“練習したつもり”になるだけで、本番には通用しません。評価観点や制度的背景を踏まえた「設定質問」があるからこそ、技術士としての判断力・倫理観・説明力が鍛えられます。つまり、的を射た質問こそが、合格への道を照らす“練習のカギ”なんです。
そこで、今回の投稿は、想定質問作成における3つのポイントを紹介します。
Point1 技術士は社会の信頼を背負ってる
<技術士試験合否決定基準の採点項目>
技術者倫理・コミュニケーション
この視点は、技術者倫理とコミュニケーションの両観点に深く関わります。技術士倫理綱領にある「公益の確保」「安全・安心の確保」「環境への配慮」は、単なる技術力ではなく、社会的責任を果たす姿勢が問われる領域です。
たとえば「地域の道路改良事業で騒音対策を講じ、住民説明会を複数回開催した」という事例は、説明責任と合意形成の実践例であり、コミュニケーション力と倫理的配慮の両方を示しています。このような事例を引き出すためには、「あなたの業務が社会に与える影響について、どのように説明していますか?」という質問が有効です。
また、技術士法の「信用失墜行為の禁止」にも配慮し、誇張や曖昧な表現を避けるような設問構成が求められます。つまり、技術士の信頼性を担保する倫理観と、社会との対話力を同時に問う設計が重要です。
Point2 コンピテンシー=技術士らしさ
<技術士試験合否決定基準の採点項目>
リーダーシップ・評価・コミュニケーション・マネジメント
技術士コンピテンシーは、技術士としての総合力を測るものであり、合否決定基準の6項目のうち特にリーダーシップ・評価・マネジメント・コミュニケーションに直結します。たとえば「若手技術者の育成において、OJTだけでなく週1回の技術レビュー会を設けた」という事例は、リーダーシップとマネジメントの発揮を示すものです。
このような行動を引き出すには、「若手技術者の育成で意識していることは?」や「どのような判断基準で指導内容を設計しましたか?」といった質問が有効です。また、「住民説明会で反対意見が多かったが、施工方法の変更提案と環境影響評価を提示し、納得を得た」という事例は、課題解決力(評価)とコミュニケーション力の両方を示しています。
質問文には“判断”“説明”“改善”といった要素を盛り込むことで、受験者の思考プロセスと行動が明確になり、技術士らしさが浮き彫りになります。
Point3 「技術士法の3義務2責務」を“生きた問い”にする
<技術士試験合否決定基準の採点項目>
技術者倫理・継続研さん・マネジメント
技術士法に定められた3義務(信用失墜行為の禁止・秘密保持・名称使用制限)と2責務(資質向上・公益確保)は、技術者倫理・継続研さん・マネジメントの観点に直結します。たとえば「協力会社との契約書に秘密保持条項を明記し、社内でもアクセス権限を限定したファイル管理を徹底している」という事例は、秘密保持義務の実践であり、マネジメント力の表れです。
また、「週1回の技術勉強会を継続し、最新の法制度や技術動向を共有している」という事例は、継続研さんと資質向上責務の体現です。さらに、「専門外の業務に関しては、技術士名称を使わず、専門家と連携して対応した」という回答は、名称使用制限の理解と実践を示しており、技術者倫理の根幹に関わります。
これらの事例を引き出すには、「業務上知り得た情報をどう管理していますか?」「技術者として資質向上のために取り組んでいることは?」などの“生きた問い”が有効です。
本サイトには、口頭試験のFAQを用意してあります。まずは、これらを眺めて傾向を掴んでみるのも手っ取り早です。また、想定質問の添削サービスもご用意していますので、心配な方はご活用を検討してくださいね(サービスの購入はコチラ)。