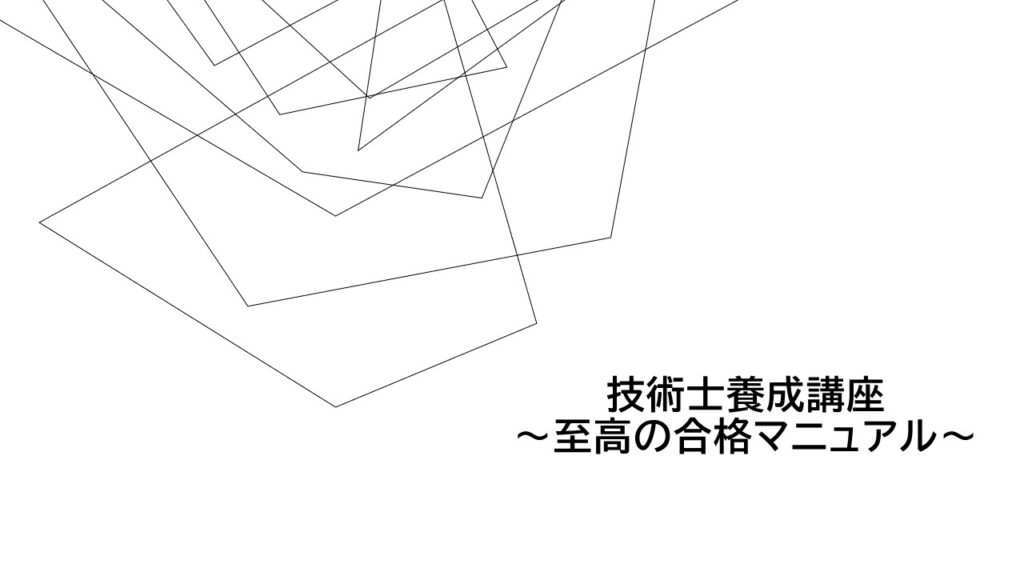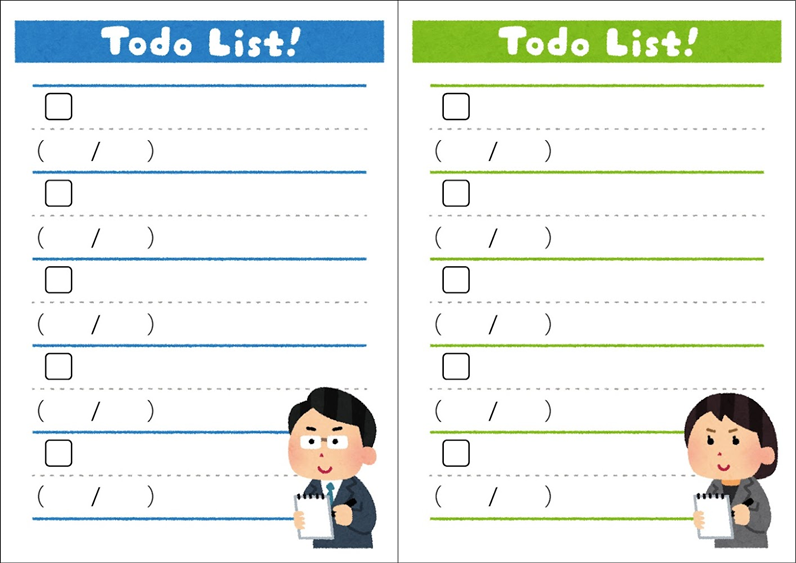合格のミニマムタスク
【 技術士 二次試験対策 】
何をやっていいか分からない人集合!
いよいよ受験申込み案内及び受験申込書様式(Excelシート)が、3月24日(月)から技術士会ホームページよりダウンロードすることができます(技術士会の案内はコチラ)。申し込んだら、後戻りはできません。心を決めたからには、記念受験、まずは様子見などといった逃げ道を作らず、徹底して合格をもぎ取りに行きましょう。
もちろん合格したいけど、どうやって勉強すればいいの、何から始めればいいのとお悩みの方、ご参集くださいませ~やることを明確にし、その心配を解消します。勉強方法が明確になりさえすれば、あとはやるだけです。これから示すタスクは、最低限の内容ですが、きちんとこなせばきっと良い結果を得ることができるでしょう。
まず、勉強方法を簡単にいうと、「論文を書きまくる」ということに尽きます。また、ただ書いて終わりでは、まったくもって意味はありません。合格レベルの論文を書きまくるということになります。この合格レベルまでもっていくのが、ひとまず大変になります。
最初から合格レベルの論文を書ける人は、ほぼいないに等しいです。したがって、最初は論文を仕上げるのにものすごい時間がかかります。この最初に費やす時間を考えるととてもじゃないけど、試験に間に合わないと悲観する人もいるでしょうが大丈夫です。間に合います。
最初は、当然なれない作業ですから、なかなか思うように書けないのですが、後半になるに従い、だんだんと感覚を掴んでくるので、初稿である程度の水準を有する論文が書けるようになります。よって、後半戦では急ピッチで論文を量産できます。さらに、この状態になれれば、予期せぬ問題が出題されても一定水準の論文を書くことができます。
初期段階で重要なのは、焦らずコツコツと論文を書くことです。
必須科目Ⅰ
① 論文のテーマを設定
過去問などを参考にテーマを予想します。ネタは、各種委員会の議論している内容、最近話題になっている時事ネタ、国土交通白書、あるいは本サイトのリアル予想問題(第1弾、第2弾、第3弾)などがあります。
② 論文作成
論文を書く際には、ロールモデル(参考にする論文)をテーマにそって再編集します。また、ロールモデルをどれにしたらよいかお悩みの方は、本サイトでひな型も用意してますのでご活用ください(ひな型はコチラ)。
③ 自分で推敲
論文を書いたら、合格論文にするための推敲が必要です。最低でも1度は読み返し、自分なりの修正を施してください。このステップが自らの能力を高めるものと心得てください。必ずやりましょう。
④ 添削
はい、ここで私の登場です。自ら推敲した論文(自分なりに完璧!と思うもの)を誰かにチェックしてもらいましょう。できれば、お近くの技術士にお願いしましょう。いない人は、どうぞ添削のご依頼をいただければ嬉しいです(サービスをご希望の方はコチラ)。
⑤ 読み返し
③~④を繰り返し論文を完成させたら、何度も読み返します。推敲の気持ちでも良いですし、関連ワードを深堀するのもよいでしょう。暗記する必要はありませんが、どんな構成でどのような材料を使ったかをすぐに思い出せるようにします。
選択科目Ⅱー1
① キーワード集の作成(50個以上)
何はなくとも、専門知識がないとⅡー1は全く書けません。よって、まず取り組むのは、キーワード集を作成します。キーワードは、やみくもに集めてもきりがないので、必須科目Ⅰで設定したテーマに関連するものから集めていき、徐々にその範囲を広げていくことが大切です。
② キーワード集の編集
ある程度キーワードが集まったら、カテゴリーを設定し分類しましょう。分類することで、断片的だった知識が体系化され、あらゆる問題に応用することができるようになります(仕事にも役立ちます)。これ結構重要です。よって、キーワード集はパソコン作業がお勧めです。
③ 論文のテーマを設定
集めたキーワードを眺めながら、出題されそうなものをピックアップします。ここでも、時事関連は出題されやすいので、最近話題になっているものを中心に選択すると良いでしょう。また、予想問題は最近の問題をアレンジして作成します。
④ 論文作成
設定したテーマで論文を書きます。選択科目Ⅱー1は、書くのは簡単です。聞かれていることを漏れなく書くだけです。ただし、聞かれていることが何なのかをきちんと把握することが求められます(Ⅱー1に限らずです)。
⑤ 推敲&添削
あとは、必須科目Ⅰと同様、自らの推敲と添削を受けてください。
選択科目Ⅱー2
① ガイドライン・手引きの収集
専門科目に関連するガイドライン・手引き・指針・示方書などを徹底的に収集します。特に法定手続きは、手順が漏れるとアウトなので必ずその流れを確認します。ガイドライン等は、全部読む必要はありません。まずは、流れが書いてあるところ(フローチャート等)を見つけましょう。
② 論文のテーマを設定
見つけてきたガイドラインからテーマを設定します。ただし、土質、コンクリート、施工計画などは、実際の実務を問うケースがほとんどなので、構造物ごとに区分して用意するなど多角的な問題を予想する必要があります。
④ 論文作成
Ⅱー2の論文作成は、基本的にガイドラインの転記になります(設計・施工系は示方書など)。問われていることに沿って、必要事項を抽出し記述します。この時、特にこの論文はスペースが少なく感じると思いますので、転記の際には極力端的に表現します。
⑤ 推敲&添削
あとは、必須科目Ⅰと同様、自らの推敲と添削を受けてください。
選択科目Ⅲ
選択科目Ⅲは、必須科目Ⅰとほぼ同様です。倫理要件がないので、解決策をたっぷり書くと良いでしょう。しかし、必須科目と同じような感覚で書くと必ず失敗します。選択科目Ⅲは、解決策はもちろんのこと、課題においても専門とする技術的記述が必要になります。
よって、勉強方法は、専門科目のより深い知識が必要になります。普段行っている業務に関連することであれば、たくさんの知識を持っていると思いますので、苦手な分野に関する知識を深めると良いでしょう。キーワード学習において、資料を読み込む際、選択科目で使えそうなキーワードも別に用意しておくのも手ですね。
しかし、用語の列挙はダメですよ。きちんと目的や具体的な内容と共に用いるのがベストです。よって、事例などにも目を通すことが重要になります。「技術士にふさわしい技術を持ってますよ」と論文でアピールする必要があります。このアピールは、解決策における具体例だと心得てください。
どうでしたか、やることがはっきりしたので、何だかやる気が湧いてきませんか。その意気です。実際手を動かしてみれば、不安や恐怖は解消されるものです。さらに、文章の書き方や注意点などが気になる人は、本サイトのメソッドやテクニックをご覧ください。
それでも不安な人向けに「技術士養成講座(至高の合格マニュアル)」を販売しています。これは、私が講習会で使用する資料をマニュアル化したものになります。秘蔵のテクニックや、論文の書き方が分かりやすく示されていますので、ぜひお役立てください(画像をクリックすると販売サイトへ移動します)。